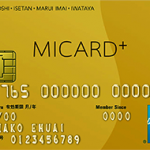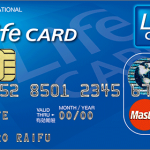QRコード決済は従来のバーコードよりも扱いやすく、利用者・経営者どちら側でも使いやすいサービスです。
ですが、QRコード決済の具体的な仕組みや、どの国発祥の技術なのか知っているでしょうか?
今回はQRコード決済の仕組みとともに、従来のバーコードとは何が違うのか、導入・利用するメリットを解説していきます。
QRコード決済の仕組み、メリット、使い方は?おすすめアプリを比較!
日本発って知ってた?QRコード決済とは

QRコード決済は、店舗情報などの支払いを成立させるための情報をまとめた二次元画像(QRコード)を用いた決済方法です。
中国などのキャッシュレス化が進んでいる一部の国ではかなり使用されている決済手段で、日本でも利用者が増えつつあります。
日本で開発された情報保存用二次元コード
QRコード決済で使われるQRコードは1994年に日本の自動車部品メーカーであるデンソーが開発した技術です。
もともとはデンソー自身が自動車部品工場で配送センターなどでの利用を考えて作られたものですが、あまりにも汎用性が高い上にオープンソース化されたことがキッカケで一気に普及しました。
そのため、QRコードの技術は世界に誇れる日本発祥の技術の一つとなっています。
QRコード決済の使い方
QRコード決済を使う流れをまとめるとこのようになります。
- 決済用QRコードを読み取る
- QRコードに記録されている店舗情報やユーザーの支払い情報などを用いて支払いが自動的に行われる
- QRコード決済サービスを運営している事業者に売上金が入る
- QRコード決済サービスごとに設定された振込日に決済手数料が差し引かれた売上金がお店の口座に入金される
このようにQRコードのおかげで簡単に決済できるようになりました。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
日本が誇る技術!QRコードの仕組み

QRコード決済の根本的な仕組みを理解するには、QRコードの仕組みを理解することが必要不可欠です。
続いてはQRコードの仕組みについて見ていきましょう
四隅にある四角とは?
QRコードには必ず四隅に四角が1~3つ印刷されています。
これはQRコードの向きを判別するために使用されているもので、四角の位置を元にどちらが上向きかどうか判断できるようになっています。
多少歪んでも正確に解析できる
四隅にある四角とは別に、少し小さめの四角が印刷されていることもあります。
これをアライメントパターンといい、アライメントパターンがあるとスキャン用カメラを斜めにかざしたとしても、正確に読み取れるようになっています。
データ量に合わせてセルが多くなる
QRコードは黒と白のドットで構成されていますが、データ量が増えれば増えるほどこれらのドットの間隔が細かくなります。
これらドットのうち一つ一つの黒いドットのことをセルといいます。
セルが小さくなって細かくなればなるほど、QRコード一つで表せられるデータ量が増え、バーコードでは扱えないデータ量もQRコード一つで扱えるようになります。
例えば、データ量が多いあまりにバーコードを3つ使わないといけない商品があったとき、QRコードであればバーコード3つ分のデータを1つのQRコードにまとめることが可能です。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
QRコード決済のメリット

QRコード決済はバーコード決済と比べてメリットが非常に大きいです。
そんなQRコード決済メリットについてひとつずつ見てみましょう。
バーコードよりも情報量を多く扱える
バーコードは扱えるデータ量が少なく、バーコード一つに事業者情報や価格などすべての情報を詰め込もうとすると足りなくなってしまうことがあります。
バーコード規格によっては可変長のものもあるため、理論上はデータ量制限はありません。
ですが、データ量が増えれば増えるほど横に長くなってしまうため、大量のデータを保存するには向いていません。
しかし、QRコードであれば、小さな正方形の二次元画像の中にバーコードに保存できるデータ量の数十倍ものデータを格納できるため、非常に使い勝手が良い規格です。
どの方向からでも読み取れる
QRコードには向きを表す四角が必ず印刷されているため、どの方向からでも読み取ることができます。
従来のバーコードの場合は必ず横向きにして読み取る必要があるため、バーコードが印刷されている場所によってはスキャンするのが大変な場合もありました。
ですが、QRコードであればそのような悩みから開放されます。
QRコードの一部がかけていても読み取れる
QRコードは一部がシミや傷などで破損していても読み取れるように作られています。
どの程度の破損状況であれば正確に読み取れるのかどうかは、QRコードの細かい規格にもよりますが、少し欠けているだけであれば問題なく利用できます。
従来のバーコードの場合は少しでも汚れているとうまくスキャンできないことがありましたが、QRコードならそういった心配も不要です。
専用のコードリーダーが不要
QRコード技術はオープンソース化(誰でも見れる状態)しているため、QRコードのスキャン技術も広く普及しています。
日常的に利用しているスマホでも読み取ることができるため専用のコードリーダーが不要となっています。
そのため、QRコード決済導入にあたって専用のスキャナーや決済端末を購入する必要がなく、コストをかけずにキャッシュレス決済を始めることができます。
バーコード決済の場合は専用のスキャナーや決済端末を購入しないといけないため、それなりの初期コストがかかってしまうことがネックでしょう。
フルカラーのロゴやシンボルなども書き込める
QRコードの「一部が欠けていても読み取れる」仕組みを利用してフルカラーのロゴなどを入れられるようになっています。
そのため、QRコード決済サービスであるPayPayやLINE PayなどはQRコード中央にロゴを印刷しています。
企業ブランドのアピールに使うことも可能であるため、汎用性もかなり高いでしょう。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
QRコード決済の導入店舗も急増中

QRコード決済を導入する店舗は全国展開している店舗はもちろんのこと、数多くの個人店も導入しています。
| コンビニ | ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、ミニストップ、セイコーマート |
|---|---|
| 百貨店・デパート | 阪急百貨店、阪神百貨店、パルコ |
| ドラッグストア | ウエルシア、ハックドラッグ、マツモトキヨシ、スギ薬局、サンドラッグ、アカカベ、トモズ、ドラッグ新生堂、くすりのハッピー、サンドラッグ、大賀薬局、アインズ&トルペ、アインズ、ココカラファイン、ツルハ、くすりの福太郎、ドラッグストアウェルネス、ウォンツ、くすりのレデイ |
| 家電量販店 | エディオン、ジョーシン、コジマ、ビックカメラ、ヤマダ電機、ケーズデンキ |
| 飲食店 | スターバックス、マクドナルド、上島珈琲店、松屋、吉野家、かっぱ寿司、牛角、和民、ピザーラ |
| ファッション・雑貨 | メガネドラッグ、AOKI、はるやま、Right-on、Zoff |
| ホテル・旅行 | H.I.S(エイチ・アイ・エス)、京王プラザホテル札幌、ホテル聚楽グループ、JRイン札幌、JRタワーホテル日航札幌、ホテルヴィスキオ大阪、ホテルヴィスキオ尼崎、ホテルグランヴィア大阪、ホテルグランヴィア京都、東横イン、ホテルマイステイズグループ、ホテル日航新潟、ホテルモントレグループ、ワシントンホテルプラザ |
| レジャー・娯楽 | Kid’s US.LAND(キッズユーエスランド)、ジャンカラ、ビッグエコー、タックルベリー、CINECITTA、ヤフオク!ドーム、よみうりランド |
これらはほんのごく一部です。
QRコード決済を導入しているお店は続々と増加しているため、将来に向けて導入して損することはありません。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
QRコード決済は導入コストが低く使いやすい

QRコード決済サービスを導入したい場合は、最低限スマホさえあれば導入できます。
もちろん複数のQRコード決済を一括で導入できる決済端末を導入することでキャッシュレス決済への対応をスムーズに済ませるのも良いでしょう。
利用者からすると現金払いより楽な上にポイントが貰える、導入する経営者側だと初期コストを掛けずにキャッシュレス決済を導入できるというメリットがあります。
また、QRコード決済サービスはクレジットカードと違って入金サイクルが早いことが多いので、資金繰りの都合でキャッシュレス決済の導入をためらっているという場合にも向いています。
まだQRコード決済の導入を行っていない場合は一度検討してみると良いでしょう。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。