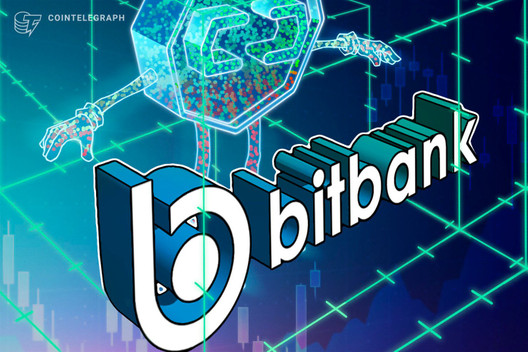1日70円で傘を持ち歩かない生活を現実のものにした、傘のシェアリングサービス「アイカサ」。代表の丸川照司氏と最高技術責任者の増田誠氏に、昨年12月にサービスが始まってからの手応えと今後に向けての展望、シェアリングエコノミーの魅力など幅広く聞いた。

【プロフィール】
丸川照司/代表取締役(写真左):台湾と日本のハーフ。東南アジアで育った期間が4割近くで中国語と英語が話せる。18歳の時にソーシャルビジネスに興味を持ち、社会の為になるビジネスを志す。マレーシアの大学へ留学中に中国のシェア経済に魅了され、大学を中退して傘のシェアリングサービスを始める。
増田誠/最高技術責任者(写真右):6歳からオンラインゲームに没頭し、9歳の時にいくつかのサイトをHTMLにて作成。その後、さまざまな言語を学び、19歳で飲食店のサイトを製作して以降、大学生活の傍ら、為替相場の分析ツールや店舗サイトを製作。
- 1. SNSやメディアに取り上げられることで認知度が高まり、ユーザー数が激増
- 2. 傘の進化としてのシェアリング
- 3. ビニール傘を「アイカサ」でリプレースすることで環境保護の一端を担う
- 4. 晴れでも雨でも「アイカサ」が救世主になる
- 5. 都内で1番利用されているのは駅の近く
- 6. 生活圏にアイカサがあれば、傘は不要
- 7. スピード感を持って新たな地域に展開したい
- 8. 誰でも納得できる分かりやすいサービス
- 9. 公共交通機関に傘を持たずに乗車できる世の中にしたい
- 10. LINEでの運用を軸にLINE以外でもアイカサの利用を可能にしたい
- 11. 「濡れない体験」を提供したい
- 12. みんなと繋がって世界を広げるところがシェアリングエコノミーの魅力
SNSやメディアに取り上げられることで認知度が高まり、ユーザー数が激増
-2018年12月にサービスリリースされて以降、反響はいかがですか?

最初は本当に小規模で始まったので、僕らからお願いして使っていただくことが多かったのですが、今年度に入ってからは多くのメディアさんに取り上げていただけるようになり、Twitterでもつぶやかれるようになってきました。それを受けて、テレビの取材とか特集を組んでいただき、ユーザー数がすごく伸びましたね。また、ユーザーさんが実際に使ってSNSに投稿されることで、認知度が高まり利用頻度も高くなってきています。
-ユーザー数が伸びたのは梅雨が関係あるのでしょうか。

メディアの方からすると、梅雨ということで傘のシェアリングを取り上げていただける頻度が増えたと思うのですが、ユーザーの伸びとしては梅雨とは関係なく、4月ぐらいから徐々に増えていき、SNSやネットメディアに取り上げていただくことでさらに増えていったと思います。
傘の進化としてのシェアリング
-「アイカサ」を思いついたきっかけを教えてください。

当たり前のことに疑問を持ったことが始まりです。例えば飲料とか食べ物とかは、自販機などが出てきたことで、見た目とか昔とは変わってきていますよね。でも、傘はずっと変わっていません。みんなが持っていて使っているのに、形も使い方も一切変わっていない。そこに何か新しいやり方があるんじゃないか、と考えたのがきっかけです。
-「傘が進化してない」ことと「シェアリング」はどのように結びついたのでしょうか?

シェアリング自体が最近すごく増えてきて、レンタルになりますが充電器やWi-Fiを借りられるサービスとか、数年前に自転車のシェアリングが始まったり、なんでもシェアリングの対象になり得るような勢いがあると思います。中国では傘のシェアリングもありますしね。これも1つのモデルにはなりましたが、新しいところで勝負できるの何かなって考えた時に、僕らお金がなかったこともあり、資金的な面でも傘はいいのではないかと思いました。
ビニール傘を「アイカサ」でリプレースすることで環境保護の一端を担う
-当初は若者のユーザー層を想定していましたか?

傘って普遍的で万人が使うものですよね。ですから、ターゲットを絞るのではなく、誰でも使えるものにしようと思いました。アイカサはスマホのLINEで友達登録することで利用できるサービスですが、LINEを使い慣れていない方でもすんなり使えるように心がけて開発しました。アプリを入れたり、WebにアクセスしてもらうよりもLINEで利用できた方が分かりやすいだろうと思ったので。もちろん、LINEということで若干若年層に寄ってはいましたけど、基本的には老若男女問わずあらゆる方をターゲットとして考えていました。
-実際に利用しているユーザー層を教えて下さい。

あらゆる方をターゲットにしてはいましたが、始まってみたら、30代ぐらいの男性がすごく多かったですね。結局、通勤で使う方が一番多かったわけです。駅や飲食店、量販店、百貨店などがアイカサのスポットなっているので、そこが生活圏と被ってくるとヘビーユーザーになっていただけますね。
-女性よりも男性に多く利用されているのですね。

女性は傘にこだわりがある方が結構いらっしゃいますよね。特に日傘は気に入ったものを買われる傾向が強いと思うのですが、雨傘も同じですよね。でも、男性は傘がないとコンビニでビニール傘を買う人が多いじゃないですか。そこをアイカサを利用することで600円くらいの出費が70円に抑えられますし、家に大量のビニール傘が溜まることもありません。溜まったビニール傘は、使うことなく廃棄しますよね。ビニール傘の消費量が8,000本と言われており、大半が使い捨てとなっていることは、環境問題とも言えます。そこを変えたいという思いが、僕らにはあって。ビニール傘をアイカサでリプレースしたいですね。
女性は傘にもデザイン性を求めているので、当初はユーザーが少なかったのですが、アイカサでも今は5種類くらいのデザインがあり、可愛いものが出てきたことで女性のユーザーも増えてきました。アイカサスポットの網羅性とともに、こうしたデザインの多様性が、女性ユーザーの伸びに影響していると思います。上野エリアに置いてあるパンダのデザインの傘は好評ですよ。
-今後、デザイン面で企業とのコラボレーションを考えていますか?

そうですね。役所や公的機関の推進ロゴとか、企業の広告を兼ねたデザインは今でもありますが、企業カラーのものも増えていくでしょうし、そういったことをまったく考えずにきれいな傘を作ろうという考えもあります。先々月に、丸井のオリジナルアニメーションの傘が出まして、PRも兼ねてはいるものの、アニメのキーデザインに寄った、ロゴも入っていないすごく可愛いデザインになっています。今後はシンプルなもの、派手なもの、可愛いもの、かっこいいもの、とどんどん増えていくと思いますよ。
晴れでも雨でも「アイカサ」が救世主になる

-日傘もリリースされましたが、反響はどうですか?

もともと日傘はすごく要望が多かったですね。最初につくった傘が、日傘の使用も兼ねてはいたのですが、雨傘として運用してきたので、日傘としては推していませんでした。でも、特に女性から「雨傘はいいんだけれども、日傘も欲しい」っていう声が多かったので、夏も盛りになるタイミングで日傘を出したのは、良かったと思っています。日傘をリリースした瞬間に「日傘出たんだ。良かった」っていう声がすごく聞こえました。
最近、雨が降るたびにTwitterで、「アイカサで助かった」みたいなつぶやきをたくさん見かけます。今後は、晴れでも雨でも、そういうつぶやきがあると、嬉しいですね。
都内で1番利用されているのは駅の近く
-サービスの開始場所を渋谷にした理由は何ですか?

スタートアップの最初の展開地として、渋谷っていうのはいい土壌だと思います。それと結構昔の話になりますが、傘のシェアリングをシブカサ(SHIBUKASA)が渋谷で展開していたのも最初の地として選んだ理由の1つです。シブカサさんが置いていたところを調べて、アイカサを置いてくださいとお願いに行きました。それと若い人たちに使っていただいて、発信してもらうことを考えていたので、そういった意味でも若者が集まる渋谷は適地と言えますね。
-アイカサスポットの選定基準を教えてください

最初は、「傘のシェアって何?」って感じで、自治体でやってる無料傘のイメージしかなくて、置いてもらうのに苦労しました。それに、置いてみないとそこで使われるかどうかもわからないですよね。なので総当たりで50か所でスタートしました。
-利用率や返却率が高いところはどこですか?

人通りが多いとか目につきやすい場所はそうでないところの10倍くらい利用率が高いですね。
-都内で1番利用されている場所はどこですか?

やっぱり駅の近くですね。渋谷でいうと、マークシティの前の新聞屋さんはすごく多いです。
-オフィスにも導入されていますが、反響はいかがですか?

担当者さんは僕らのことに共感して置いてくれますが、実際に使う人は社員さんですよね。最初からみんなで使ってくださるところもあれば、「これなんだろう?」っていうところから始まって、じわじわ広がっていくところもあります。
生活圏にアイカサがあれば、傘は不要

-利用頻度の高い方の利用回数は1か月あたりどれくらいですか?

多い方だと10回ぐらいですね。もちろん天気によりますが。最近ユーザーさんの中で、アイカサを使うことによって傘を持たなくなったっていう方が出てきて、すごく嬉しいなと思っています。そういう方は、ご自身の生活圏にアイカサのスポットが揃っている方ですね。家の近くにあって駅にもあれば、傘をまったく持たなくてもいいわけです。それが、僕らのやっているサービスのゴールと言えるので、それも少し見えてきましたね。
これからの課題としては、完全に生活圏にアイカサスポットが根付いている方がまだ少ないので、自宅を出たところ、駅、オフィスのそれぞれにアイカサスポットを作ることですね。
スピード感を持って新たな地域に展開したい
-ユーザーからの要望が多い機能はありますか?

TwitterやLINEでの問い合わせで要望が多いのは、アイカサのマップのスポットが増えすぎたためにマップが固まってしまって見づらい点を改善してほしい、という意見は多いですね。最初にユーザーが見るのはマップなので、自分の場所や行き先をもっと素早く見られるようにしてほしいっていう声に応えるために、開発としては力を入れていくところです。
ただ、一番多いのは「この駅に設置してほしい」とか、福岡と東京以外の全国各地からも「ください」っていう声が一番多いですね。
-東京の次に福岡を選んだ理由を教えてください。

福岡は行政も含めてスマートシティの戦略を推し進めています。僕等は最初クレジットカード決済だけだったのですが、LINE Payを導入しました。そのあと福岡で展開し始めて驚いたのは、今は屋台もQRコード決済ができたことです。企業も行政も町全体でスマートシティの戦略を進めているのが、傍から見ていても感じましたし、実際に行って話してみて、僕らのサービスとすごく相性がいいんじゃないかと思い、福岡を選びました。
福岡での反響は、すごく大きかったですね。僕も福岡で設置を手伝いましたが、みんな興味津々で見ていますね。渋谷で設置したときはそういう人があまりいませんでした。でも、福岡は設置していたら「これなんですか?」ってよく聞かれます。それも若い人だけじゃなくて老若男女問わず、すごく興味を持ってくださったので福岡を選んで良かったなと思いました。
-次のターゲットは考えていますか?

いろいろ検討はしていますが、観光地とか、人の往来が多いところを念頭に置いています。それから、福岡みたいに行政の理解があると非常に助かりますね。例えば、関西で飲食店1軒に置いてくださいって言われても、そこで借りて返すだけになりますよね。少し集中した展開ができるとありがたいなと感じているので、そういうところを念頭に置きつつ検討しています。こういったことはスピードも必要ですので、常にどんどん新しい場所を探して設置していくことを考えています。
誰でも納得できる分かりやすいサービス

-ここまでのニーズがある理由は何でしょう?

分かりやすいサービスだからかもしれませんね。「傘のシェア?たしかに傘忘れる。ビニール傘の使い捨ては、環境に悪いね。駅にあったら便利だし、お店にあったらお客さんにも貸せるよね」って、決裁者の方にも伝えやすいですし、営業している感覚もなく、内容を伝えれば誰もが納得できますよね。
-アプローチは企業側からが多いですか?

今は7割ぐらいが企業さん側からになっています。ただ、お問い合わせいただいた企業さんすべてに置かせていただいているわけではありません。エリアで1か所だけでは利用しづらいですし、場所は選ばせてもらっていますね。ただ、都内はあらゆる場所に置いていこうと考えているので、ほぼ断ることはありませんよ。
公共交通機関に傘を持たずに乗車できる世の中にしたい
-ほかのシェアリングサービスとの相性はいいですか?

すごくいいと思っています。例えばアイカサのユーザーさんが、モバイルバッテリーのシェアリングのユーザーと合致することはないと思いますが、モバイルバッテリーを使ってる人で傘を使わない人はいないですよね。そういう意味では、シェアリングも含めてほとんどすべての事業とすごく相性がいいと思っています。
-今後連携していきたいジャンルを教えてください。

意外と各シェアリングの事業者さんと組んでいる事例があまりないので、シェアリングとシェアリングっていうのもすごくやっていきたいと思っています。あとは交通系ですね。全国に広げていくに当たって、電車とかバスとか新幹線、飛行機が入り口になると思っています。やっぱり電車やバスに乗る時に、濡れた傘を持っているのは嫌じゃないですか。ですから、傘を乗車駅で返して下車駅で借りることははすごく便利だと思っているので、今後、交通系の企業と一緒にやっていきたいですね。
LINEでの運用を軸にLINE以外でもアイカサの利用を可能にしたい
-今後、LINE以外での運用を予定されていますか?

LINEはみなさん使われているので、入り口として最適だと思っています。LINEの中でアイカサを借りられるミニプロガラム的なやり方は、今後LINEさん側の変化に合わせていく形で続けていきたいですね。一方で、LINEを使っていない方でも使えるような仕組みは用意したいと考えています。そうすると、外国人旅行客の方にも使っていただけるんじゃないかな。
「濡れない体験」を提供したい
-アイカサのメリットを教えてください。

傘を持ち歩かなくていいとか、どこでも借りて返せるのもメリットではありますが、僕らは「濡れない体験」を提供したいと考えています。濡れない体験を提供したいっていう理念でやっているので、それが一番のメリットだと思います。日傘に関していえば、「日焼けをしない体験」です。もちろん僕らは傘が大好きですが、傘は手段のひとつであって、傘を持たなくても濡れない、傘を持たなくても日焼けしないって、筋が通るような世界を作りたいと思っていて、そこがメリットだと思います。
みんなと繋がって世界を広げるところがシェアリングエコノミーの魅力

-シェアリングエコノミーの魅力を教えてください。

シェアリングエコノミーっていうものに触れてみると、すごく便利で世界が広がると思えます。自分が買ったり、使っているものでだけで完結しない、世界の広がりが見えてくる世界ではありますよね。エコとか環境にいい面もありますが、みんなと繋がって世界を広げるところが魅力じゃないかなって思っています。
-今後、シェアリングがどのように拡大していくと思いますか?

シェアリングエコノミーって、1回体験した人はずっとそこにいて、みんな知らないから入ってこないだけだと思っています。傘やモバイルバッテリーや自転車っていう、生活に根付くものでシェアリングが広がってきているので、例えばアイカサが全国に広まって、すべての人の目につくようになれば、みんなが1回でも体験しようと思ったタイミングで爆発的に伸びると思いますよ。
-貴重なお話をありがとうございました!
インタビュー:NANASE/撮影:堅田ひとみ