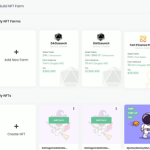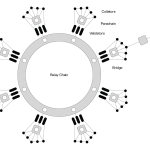暗号通貨・ブロックチェーンの研究開発と、その研究開発が実際に身を結んで製品ローンチまで結びつくまではどのような時間軸を必要とするのでしょうか。これは実際に何年くらいと一概には言えませんが、大まかな感覚を持っておくことは一定の価値があるでしょう。
投資判断にも役立つ時間軸への理解
というのも暗号通貨・ブロックチェーンのホワイトペーパーや論文は日々発表されており、さらにこの業界の特有な事情としては世には論文しか出ていない状態でトークンが販売されていたり、ベンチャーキャピタルから出資を受けているということは珍しくありません。そのため論文公開とプロダクトローンチの時間軸の感覚は投資判断にも役にたつはずです。最近注目されるプロトコルやブロックチェーンの最初の論文やホワイトペーパーが公表された時期は下記の通りです。
- Tendermint(COSMOS HUBのコンセンサスアルゴリズム)の論文:2014年
- Tezosのペーパー:2014年
- Filecoinのペーパー:2014年
- Dfinityのコンセプト提案:2015年
- Polkadotのコンセプト提案:2016年
- Lightning Networkの論文:2016年
- Plasmaの論文:2017年
COSMOS HUBのコンセンサスアルゴリズムのテンダーミント(Tendermint)は既に数多くのブロックチェーンで応用運用がなされています。イオス(EOS)やトロン(TRON)も同論文に大きい影響を受けてると考えて良いでしょう。ファイルコイン(Filecoin)は2019年末にテストネットが公開され、2020年にメインネットが公開される予定です。
双方向のペイメントチャネルのネットワークであるライトニング・ネットワーク(Lightning Network)は2018年頃からネットワークが立ち上がり始め、2019年では活発には利用されていないものの、ようやくユーザーエクスペリエンスを向上させるアプリケーションが登場し、ビットフィネックス(Bitfinex)など一部取引所でサポートが始まっています。
おおよそ、これらを概観すると、R&Dの最初の発表からプロダクションまでいずれも5年前後の時間がかかっていると言えるでしょう。なおR&D自体は最初の論文発表前から着手されてるので、R&D開始時間から数えると製品ローンチまではさらに時間がかかっていることになります。
ちなみに参考になるかは難しい例えですが、ビットコインのホワイトペーパーは2008年に公開され、2020年現在に時価総額は2兆円、新しいアセットクラスとして存在が確立されつつあるという状況です。悪く言えばまだ生活には浸透していません。
移り変わる業界のフェーズ
業界トップのクリプトファンドであるポリチェーン・キャピタル(Polychain Capital)の最高経営責任者(CEO)であるオラフ・カールソン・ウィー(Olaf Carlson-Wee)は、2013-2015年頃は低レイヤーの分散技術の研究者が業界に参入していたが、2019年の今はプロダクトフォーカスのアプリケーションエンジニアが業界に参入していることを指摘しています。
プロダクトフォーカスのアプリケーションエンジニアはGoogleやAppleなどの企業を退職して暗号通貨業界に入るトレンドが生まれてるといいます。2013-2015年頃、業界は低レイヤーの分散技術の研究者を必要としており、彼らはコアプロトコルの理論を構築しました。今ではその実装もかなり進み、そのコアプロトコルを使用して、実際にユーザーが使用するプロダクトをマーケット戦略を持って開発できるエンジニアが必要とされています。
まさに気づいたらブロックチェーンを使っていたというようなプロダクトで人々に必要とするものを生み出せる開発者が求められており、業界のフェーズが移り変わっているとも言えるでしょう。
【こんな記事も読まれています】
・2020年は金融機関がブロックチェーン技術を受け入れる転機の年
・ブロックチェーン・ウォレットなどの採用は急速に進む、ドイツ銀行がレポート発表
・ブロックチェーンのノード運用の困難さと意味すること
d10n Labのリサーチコミュニティでは、ブロックチェーン業界の動向解説から、更に深いビジネス分析、技術解説、その他多くの考察やレポート配信を月に20本以上の頻度で行なっています。コミュニティでは議論も行えるようにしており、ブロックチェーン領域に積極的な大企業・スタートアップ、個人の多くに利用頂いています。
▼d10n lab 未来を思考するための離合集散的コミュニティ
https://d10nlab.com