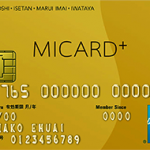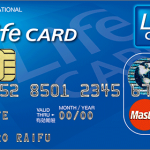近年は、政府が副業解禁を打ち出したことから、資産運用である株式投資、FX、投資信託、ETFなどにサラリーマンからも注目が集まっています。
その投資方法の中でも、ロボアドバイザーも注目を集めています。
今回は、ロボアドバイザーと呼ばれる新しい投資スタイルと投資信託との比較を行い、何が違うのか具体的に解説します。
ロボアドバイザーとは

ロボアドとも呼ばれるロボアドバイザーとは、インターネット上で投資信託の診断やアドバイスを行ったり、売買の補助や自動運用、管理などを行ってくれるサービスです。
最適な資産配分や投資対象の助言だけを行うタイプ助言型と、助言と運用までを行う一任型の2つがあります。
一任型については、投資信託の提案や、運用プランの提案に了承できれば、ロボアドに資産運用を任せることができます。
ロボアドバイザーの投資対象
ロボアドの投資対象は、運用している事業者のサービスによって異なります。
主に海外上場投資信託(ETF)や国内投資信託が対象です。
ロボアドバイザーの運用コスト
ロボアドバイザーは基本的に購入手数料が無料の場合が多いですが、運用手数料については「THEO(テオ)」や「Wealthnavi(ウェルスナビ)」などのロボアド大手では信託財産に対して年1%の手数料(3000万円までの部分)が掛かります。
投資信託とは

投資信託とは、多数の投資家から資金を集めて、それを元に運用の専門家が株式や債券などに投資し、運用で得た利益を投資家に還元する仕組みの金融商品のこと。
投資信託を運用するのは「販売会社」、「委託会社」、「受託会社」の3社です。
投資家にとって、投資信託からの分配金や償還金、売却による売却益がリターンになります。
投資信託の種類
投資信託の投資対象は、株式、債券、不動産などの多様なジャンルの資産で、国内から海外金融商品までを対象とするものもあり様々です。
資産クラスによる分類は次の主な4種類です。
- 国内株式型
- 海外株式型
- 国内債券型
- 海外債券型
これ以外にも国内不動産、海外不動産や金・原油などの実物資産を対象とする投資信託もあります。
投資信託の運用コスト
投資信託で運用を行う際に掛かるコストには以下の4種類があります。
- 販売手数料
- 信託報酬
- 監査報酬
- 信託財産留保額
販売手数料は投資信託を購入する際の費用であり、信託報酬は運用に伴う費用(運用報酬、信託財産の管理費)が信託財産留保額から差し引かれます。
監査報酬は投資信託を監査する法人に対して支払う報酬であり、信託財産留保額は投資信託そのものを解約する際に投資家側が負担する金額を指します。
これら4つのコストは、利用するサービスによって内容や金額が変動します。
必ず購入前に確認を行い、どれくらいのコストが発生するのかを試算しておきましょう。
ロボアドバイザーと投資信託の違いは?

この項目では、ロボアドバイザーと投資信託の違いを様々な観点で見ていきます。
投資商品が違う
投資信託は、投資家が自分で投資信託を選んで投資を行う形であり、ロボアドバイザーは個人の情報や運用イメージをチェックし、最適な投資信託やETFを選択し、購入、最適化を行います。
両者の投資対象の範囲や数は異なりますが、主な対象が投資信託及びETFである点は一緒です。
投資対象に大きな違いはなく、根本的には、投資信託は投資家自身で投資対象を選定・購入などを行う必要がありますが、ロボアドバイザーはそれらを代行して行ってくれるという点が違いでしょう。
運用する手間が違う
結論から話すと、ロボアドバイザーを利用した方がある程度の手間を省くことが可能です。
個人が行う投資信託の投資方法の手順を示すと以下のようになります。
- 投資対象の資産配分を決定する
- 投資信託の商品を選定する
- 証券会社等へ入金する
- 投資商品を発注する
- 分配金の再投資、償還後の新規投資等を検討する
- 投資目的や目標に応じてポートフォリオを修正する
投資信託の投資は、資金を一つの商品に充てるのではなく、複数の商品に分散投資するケースが多いです。例えば、国内株式型、海外株式、国内債券型と海外債券を2:2:3:3の割合で投資するといった方法です。
そのため、投資家自身が投資対象の収益性やリスクを考慮して選ぶ必要があります。
もちろんこの作業は投資信託をする上の醍醐味である一方、投資経験が浅い方などには選択する基準が少ないために時間が掛かってしまう作業です。
その結果、投資までの時間が掛かり過ぎたり、コストパフォーマンスの良くない商品を選択してしまう場合もあります。
ロボアドバイザーを利用すると自分で投資商品を選ぶ手間がなくなり、投資信託よりも簡単で手早く始められます。
積立投資も可能であり、分配金の再投資や市場の動向に合わせたポートフォリオの最適化を自動で行う点も初心者向きです。
このようにロボアドバイザーは、個人で投資信託を行う大半の作業や手間を自動で行ってくれるため、「投資知識がない」、「経験が浅い」という方に合った投資方法です。
リスクが違う
投資信託は自分の判断で商品のリスクを評価して選ぶ必要があります。
その反面、ロボアドバイザーは投資家のリスク許容度に応じた商品を選ぶのが特徴です。
最先端の投資理論を基にした投資システムなどによって、投資家のリスク許容度に適したポートフォリオを提案します。
また、ビックデータや市場データなどから投資対象などの下落を予想、自動的にリスクの低いポートフォリオに構成し直すことも簡単です。
このような点から、ロボアドバイザーの個人による投資信託以上のリスク分散が期待出来ます。
投資額が違う
投資信託もロボアドバイザーも1万円程度の資金で投資を始めることが可能ですが、投資信託では100円単位の積立投資も可能です。
ロボアドバイザーは、提供会社によって最低投資金額10万円といった設定もありますが、THEO(テオ)などのように毎月1万円から積立可能な場合もあります。
運用コストが違う
運用コスト面では大きな差はありませんが、購入時のコストは投資信託の方が高いです。投資信託では0%〜3%掛かるのに対して、ロボアドバイザーは無料の場合がほとんどであるため、運用する際には見ておきたいポイントです。
どちらも積立投資することができる

投資信託、ロボアドアドバイザー共に積立投資ができます。最低積立金額には差があり、投資信託では100円単位の積立投資が可能です。
ロボアドバイザーは最低投資金額が10万円の設定を設ける場合がほとんどですが、サービスによっては毎月1万円から積立投資が可能なタイプもあります。
おすすめのロボアドバイザー3選

ロボアドバイザーと投資信託の特徴を理解した上で資産運用を始めよう

今回は、ロボアドバイザーと投資信託の違いに焦点を当てて解説しました。
投資信託は自分で商品の選定を行うことから始めるために、ある程度の運用知識がある方におすすめです。
ロボアドバイザーは、商品の選定から運用までを全てAIが行ってくれるため、投資初心者におすすめのサービスと言えるでしょう。
自身の趣向に応じて使うサービスを上手に選定しましょう。