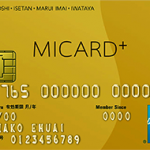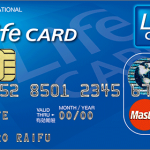ユーザーが使いたい機能をクラウド型で提供するSaaS(サース)には、サブスクリプション方式など、従来にはないビジネスモデルが誕生しています。
この記事では、ベンダー(提供側)にとってのメリットに注目し、現状のSaaSに見られる特徴と今後の展開について解説します。
SaaSのビジネスモデル事例

最近増えてきた「サブスクリプション」とは、動画や音楽配信ビジネスにおける「定額制」と同様の考え方です。
これまでレコードショップのような販売店では、コンテンツを1本ずつ取り引きしていましたが、オンライン配信サービスの中には、 1ヶ月の費用を支払えば「見放題」となるシステムが採用されています。
SaaSにおけるサブスクリプション方式も同じく、アプリケーションを利用する期間や、ファイル容量で料金が発生するシステムとなっています。
サブスクリプションに関する近年の大きな変化といえば、「Microsoft Office 365」が挙げられるでしょう。
ワードやエクセルといった従来のパッケージソフトをクラウドに移行することで、パソコン、タブレットといった端末間のファイル共有が自由自在になりました。
会社のパソコンで作ったファイルを自宅のタブレットで見直したり、出張先のスマートフォンで確認したりと、自由な環境で働く「ノマドワーキング」の実現を後押ししています。
サブスクリプションの特徴と利用者・提供者のメリット

ユーザーである利用者にとっては、何らかの機能を使いたい時に、高額なパッケージソフトを購入する必要がなく、使いたい分だけ契約するメリットがあります。
また、SaaSを提供する側のベンダーにとっても、革新的なオプション機能を一部のユーザーに提供して、ビジネスとして成立するかテストできるなどの特徴もあります。
SaaSのメリットについて、両方の視点から確認してみましょう。
ユーザーメリット:お試し期間があり、使い切りで利用できる
利用者としては使い切りというメリットが大きいのに加えて、アプリケーションを自分のパソコンにインストールする必要がない、という手軽さがあります。
・使いたい期間や機能だけを絞り込んで利用できる
・パッケージの管理が不要
・一定の試用期間がある
「パッケージの管理」に関して、個人のパソコンであれば、それほど気にならないかも知れませんが、複数台のパソコンを管理する際には非常に重要です。
ネットワーク管理者が社内のパッケージソフトを管理する際には、ソフトのバージョンアップなどの保守に時間が取られてしまうため、SaaSのようにベンダー側でアップデートしてもらえるサービスには大きなメリットがあります。
また、多くのSaaSでは 一つのIDで、複数の端末が利用できるサービスを提供しています。たとえば、アップルの「iCloud」で提供されているファイルストレージであれば、Mac、iPhone、iPad それぞれの端末で、ファイルを共有することが可能です。
ベンダーメリット:フリーミアムによってユーザーの囲い込みが可能
手軽に導入できる、というユーザーメリットは、ベンダー側のビジネスモデルにも直結しています。
・フリーミアム (無料戦略)が採用できる
・ソフトウェアの改ざんやコピーが事実上不可能
・マーケットプレイスの開放など、ユーザーを囲い込みしやすい
フリーミアムとは、基本サービスを無料で提供して追加機能に課金する仕組み。ニコニコ動画やYoutubeといった動画共有サービスでも採用されています。
これと同じく、SaaSではハイエンドユーザーに対して特別な機能を提供しやすいメリットがあります。具体的には「AIアシスタント」といった機能は、随時改修が必要であるためパッケージ形態であれば、頻繁なアップデートが必要です。
そのような更新処理に対しても、SaaSであれば「実験的な機能」として導入し、利用者が少なければ終了させることができます。
「物理的なパッケージが存在しない」という点は、ソフトの違法コピーも防いでいます。映画・音楽・ソフトウェアと、さまざまな媒体が違法コピーを防ぐためのプロテクトをかけてきましたが、それらの対策が不要となります。
さらに、SaaSは一種のコミュニティを形成します。利用者間でのファイル共有を通じて、「マーケットプレイス」が作れる点も大きいでしょう。
たとえば、画像処理アプリをSaaSで提供した際に、ユーザーが写真をそのサービス内で販売することができる仕組みです。Adobe「データマーケットプレイス」などが、その例にあたります。
SaaSでは人工知能(AI)などの機能追加も盛ん

SaaSのようなクラウドサービスといえば「Evernote(エバーノート)」「Dropbox(ドロップボックス)」といったファイルストレージが有名ですが、オフィス製品がSaaSで提供されているように、現在ではさまざまな取り組みがスタートしています。
人工知能/機械学習の応用
企業の営業を支援する「Salesforce.com(セールスフォース・ドットコム)」では、顧客のデータを蓄積することで、将来予測を可能とする人工知能機能が実用化されています。
画像処理の「cre8tiveAI(クリエイティブAI)」では、写真・イラストにある不要なモノを除去するシステムに、補完AIを採用しています。
人物写真の背景だけを切り抜く機能は、ほかの画像処理アプリでも使われていますが、アプリケーションを使い慣れている人でなければ綺麗に切り取りできませんでした。
それに対して同サービスでは、AI技術を活用することで「ドラッグ&ドロップで簡単操作」という手軽さを実現しています。
IoT、アプリケーションの開発分野
IoT分野では「conect+(コネクトプラス)」が、スマートフォンアプリを簡単に開発できる場所をSaaSとして提供しています。
マイクロソフト社の「Azure」は、SaaSを動かすプラットフォームであるPaaS(パース)ですが、その基盤においても、IoTの需要が高まっています。
同プラットフォームの中にある「Azure IoT Central」では、IoTとSaaSの組み合わせを「サービスとしてのソフトウェア」と位置づけて、開発の土台を作っています。
どの例も、サブスクリプション方式を採用することで、ユーザーは「お試し期間」の権利を得ることができますし、ベンダー側はユーザーがサービスを利用するハードルを下げて、利用傾向をいち早くリサーチすることが可能となっています。
デジタルデータのメリットを活かしたビジネスモデルSaaSの将来性

これまで売買されてきた物品と違って、デジタルデータには「時間が経っても劣化しない」という特徴があります。SaaSが従来の売買モデルとは一線を画した仕組みとなっているのは、このデジタルデータの特徴を捉えている点にあります。
レンタルCDショップの場合、1枚のCDを何回も貸し出すと、いずれかのうちに傷がついて音楽が再生できなくなります。そのため、料金には一定の経費を乗せる必要がありますが、デジタルデータなら不要になります。
劣化・欠損による経費が生まれないため、サブスクリプション方式のような「定額制」を採用しても、ベンダー側は利益を上げることができるのです。
このようにSaaSは、ユーザーとベンダーともに導入しやすい仕組みであるため、大きな企業だけでなくスタートアップ企業も、顧客へサービスを提供する方法としてSaaSを採用しています。