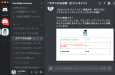【速報】金融庁、暗号資産105銘柄を金融商品に格上げへ【11月16日】
最終更新:2025年11月16日 10:00頃 | 次回更新予定:重要な進展があり次第
 30秒要約
30秒要約
 何が起きた?
何が起きた?
金融庁が、ビットコインなど暗号資産を金融商品取引法(金商法)の対象となる「金融商品」として位置づける方針を正式に固めた。
 いつ?
いつ?
2026年の通常国会に金商法改正案を提出することを目指し、制度設計の最終調整段階に入っている。
 対象は?
対象は?
国内の交換業者が取り扱う105銘柄(ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)など主要銘柄を含む)が一括して金商法の規制枠組みに移行予定。
 誰に影響?
誰に影響?
暗号資産を保有・取引している個人投資家全般、暗号資産交換業者、発行者・プロジェクト関係者、そして今後参入を検討する企業や金融機関。
 現状は?
現状は?
・金融庁が金商法適用の基本方針を固めた段階
・金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ(WG)」では、制度設計を巡る議論が第5回会合まで進行し、大詰めに差し掛かっている。
 詳細情報
詳細情報
金商法適用の概要
金融庁は、暗号資産(仮想通貨)を「投資の対象」としての実態に合わせ、現行の資金決済法中心の枠組みから、金融商品取引法(金商法)による規制へと本格的に移行する方針を明らかにしました。
報道によると、対象となるのは国内の暗号資産交換業者が取り扱う105銘柄。この中には、以下のような主要銘柄が含まれます。
- ビットコイン(BTC)
- イーサリアム(ETH)
- 他、国内取引所に上場している主要アルトコイン など
これら105銘柄について、情報開示義務とインサイダー取引規制を中心とする金商法上のルールが適用される方向で検討が進んでいます。
金商法改正案は、2026年の通常国会への提出を目指しており、詳細な条文案の詰めや関係省庁との調整が今後の焦点となります。
主な規制内容
1. 情報開示義務の強化
交換業者に対して、取り扱う暗号資産について投資判断に必要な情報を体系的に開示する義務が課される見込みです。報道・WG資料を総合すると、以下のような項目が想定されています。
- 発行者の有無・主体
- トークンに発行主体がいるのか、完全に分散したプロトコルなのか
- 開発チームや財団などのガバナンス体制
- ブロックチェーン等の基盤技術
- どのチェーン上で動作しているか(例:ビットコイン、イーサリアム、独自チェーン 等)
- コンセンサスアルゴリズム(PoW、PoSなど)の概要
- 価格変動リスク
- ボラティリティの高さ
- 流動性状況、主要な取引市場
- 過去の価格推移・急変動リスク
これにより、株式や投資信託と同様に「目論見書的な情報」が整備される方向で議論が進んでいます。
2. インサイダー取引規制の導入
今回の金商法化の「目玉」の一つが、暗号資産に対するインサイダー取引規制の導入です。
対象となる「重要事実」として、現時点で議論されているのは主に以下のような内容です。
- 取引所における銘柄の新規上場・上場廃止(取り扱い開始・廃止)
- 発行者・プロジェクトの破産・経営破綻・重大な経営方針変更
- ネットワークやプロトコルに関する重大な不具合・ハッキング・セキュリティインシデント
- 投資家保護上、価格に大きな影響を与えうるその他の重要情報
発行者や交換業者の役職員・関係者が、これらの未公表情報を知りながら売買を行った場合、株式と同様に違法なインサイダー取引として課徴金・刑事罰の対象となる方向で検討されています。証券取引等監視委員会(SESC)に対し、暗号資産取引の監視権限を付与する案も報じられています。
3. 税制改革の検討(最大55% → 約20%へ?)
税制面では、金融庁が2026年度税制改正要望の中で、暗号資産取引について申告分離課税(約20%)への移行を正式に要望していることがポイントです。(金融庁)
- 現行
- 利益は「雑所得」として総合課税(最高約55%)
- 損失の繰越控除なし
- 要望内容(案)
- 株式・FXなどと同様の申告分離課税 約20%(20.315%程度)
- 暗号資産取引の損失を3年間繰り越し可能とする案
- 課税タイミングを「暗号資産同士の交換時」から、
法定通貨への交換時などに一本化する見直しも議論中
重要なポイント
まだ「決定」ではなく、あくまで金融庁・業界団体からの要望段階であり、最終的には与党税制調査会・国会での審議を経て決まります。
とはいえ、
- 金商法への移行と合わせて、
- 税制でも株式と同等の扱いに近づける方向性は、公式資料・各種報道でほぼコンセンサスになりつつある状況です。
 影響範囲
影響範囲
| 対象 | 影響度 | 内容 |
|---|---|---|
| 個人投資家 | 高 | 税負担軽減の可能性、情報開示充実による投資判断のしやすさ、公正な市場環境の整備 |
| 暗号資産交換業者 | 高 | 情報開示義務の新設・強化、インサイダー規制への対応、システム・コンプラコスト増 |
| 発行者・プロジェクト関係者 | 高 | 未公開情報の取扱いルールの厳格化、開示・IR体制の構築が必要 |
| 金融機関・証券会社 | 中 | 将来的な暗号資産・ETF取り扱いの前提条件として、法的枠組みが明確化 |
| 市場全体 | 中 | 信頼性・透明性の向上、海外投資家も参加しやすい制度的な成熟へ |
 重要ポイント
重要ポイント
投資家への影響
 ポジティブ要素
ポジティブ要素
- 税率が最大55% → 約20%前後(申告分離課税)に下がる可能性
- インサイダー規制・情報開示強化により、価格操作や不正取引への抑止力が高まる
- プロジェクトや基盤技術の情報が整理され、「よく分からないまま買う」リスクが減る
 注意すべき点
注意すべき点
- 税制改正はまだ要望段階であり、
→ 実際の適用時期・内容は2025年末〜2026年以降の税制改正・国会審議次第 - それまでは
→ 現行どおり雑所得として最高55%の累進課税が適用される - 105銘柄以外の暗号資産や、海外取引所でのみ扱われるトークンの扱いについては、
→ 今後の制度設計・追加ルール待ち
業界への影響と懸念
金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」では、規制案に対する賛否両論が出ています。
- 暗号資産交換業者の約9割が赤字とされる厳しい経営実態
- その中で、金商法レベルの厳格な規制を導入すると、
- 「規制が重厚すぎて業界が持たない」という悲鳴にも近い声
- スタートアップ・中小事業者にはコンプライアンス負担が大きすぎる、との指摘
- 一方で、投資家保護の観点から
- 「暗号資産も他の金融商品と同等の規律を」という強い要望もあり、
- 『保護とイノベーションのバランス』が最大の論点になっています。
WGの第5回会合(11月7日)では、暗号資産レンディングや銀行・保険会社による取り扱い要件も議論され、制度設計は最終段階に差し掛かっている状況です。
 今後のスケジュール(想定)
今後のスケジュール(想定)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 〜2025年度内 | 金商法改正案の詳細設計/金融審議会WGでの最終報告取りまとめ |
| 2025年末 | 2026年度税制改正大綱の策定(暗号資産の分離課税が盛り込まれるかが焦点) |
| 2026年通常国会 | 金商法改正案の国会提出・審議(成立すれば、施行までに一定の準備期間が設定される見込み) |
| 法成立・施行後 | 情報開示義務・インサイダー規制など、段階的に施行される可能性 |
※上記は報道・公表資料をもとにした見通しレベルであり、実際のスケジュールは政治状況や審議状況により前後する可能性があります。
 背景情報
背景情報
なぜ今、金商法適用なのか
日本の暗号資産市場は、
- 口座数:延べ1200万口座超
- 利用者預託金残高:5兆円超
とされ、もはや「少数のマニア向け」ではなく、一般的な投資商品に近い規模に成長しています。
しかし現行では、
- 規制の中核は資金決済法(決済手段/送金インフラとしての位置づけ)
- 投資商品としての情報開示・インサイダー規制は十分とは言えない
というギャップがあり、この「市場実態との乖離」が長年の課題でした。
さらに、
- SNSを使った偽の投資勧誘
- 海外取引所・怪しい案件を通じた詐欺
- 出金トラブルや、ハッキング被害
などに関する相談が、金融庁の相談窓口に月300件超寄せられているとされています。
こうした事情から、
「投資実態に合わせて、金商法でしっかり保護・監視する」
という方向性が、政府・金融庁・有識者の間で明確になったと言えます。
国際的な動向
欧米でも、
- 暗号資産を証券・金融商品として位置づけて規制する動き
- インサイダー取引・市場操作への監視強化
- ETF(現物・先物)などの上場商品を通じた投資の「囲い込み」
といった流れが加速しています。
日本が金商法の枠組みを導入することで、
- 国際的にも遜色ない投資家保護・市場監視体制
- 税制面でも分離課税20%前後が実現すれば、
→ 海外と比べても「極端に不利ではない」水準へ改善
といった効果が期待されています。
日本の主要仮想通貨取引所
BitTrade(ビットトレード)
特徴
- 豊富な暗号資産銘柄を取り扱い(29銘柄)
- 高度なセキュリティシステム
- 初心者から上級者まで対応のUI/UX
主要手数料
- 売買手数料:販売所スプレッド、取引所0.05~0.2%
- 入金手数料:銀行振込無料
- 出金手数料:330円
- 送金手数料:銘柄により異なる
最小購入額:販売所500円、取引所0.001BTC 積立サービス:対応 スマホアプリ:高機能アプリあり セキュリティ:コールドウォレット、2段階認証 向いているユーザー:多様な銘柄への分散投資を検討している方
SBI VCトレード
特徴
- SBIグループの信頼性と実績
- 業界最低水準の手数料体系
- 充実したレンディングサービス
主要手数料
- 売買手数料:無料
- 入出金手数料:無料
- 送金手数料:無料(業界最高水準)
取扱銘柄:23銘柄 最小購入額:500円 積立サービス:毎月500円から レンディング:年率最大8% セキュリティ:金融庁認可業者の高度なセキュリティ 向いているユーザー:手数料を最小限に抑えたい初心者から中級者
Coincheck(コインチェック)
特徴
- 国内最大級の暗号資産取引所
- 初心者にも分かりやすいシンプルな操作性
- NFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」運営
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料、取引所無料
- 入金手数料:銀行振込無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料:407円
- 送金手数料(BTC):0.0005BTC
取扱銘柄:29銘柄 最小購入額:500円 積立サービス:月1万円から(14銘柄対応) 特別サービス:Coincheck NFT、IEO実施経験 向いているユーザー:暗号資産初心者、NFTに興味がある方
bitbank(ビットバンク)
特徴
- 全暗号資産取引量国内No.1の実績
- 高度な取引ツールとチャート機能
- Maker手数料マイナス(報酬システム)
主要手数料
- 売買手数料:Maker -0.02%、Taker 0.12%
- 入金手数料:無料
- 出金手数料:550円/770円(3万円以上)
- 送金手数料(BTC):0.0006BTC
取扱銘柄:38銘柄(国内最多クラス) 最小購入額:0.0001BTC 積立サービス:なし(現在) セキュリティ:コールドウォレット、マルチシグ対応 特殊機能:リアルタイム入金、高度な注文機能 向いているユーザー:取引量の多いアクティブトレーダー、上級者
OKJ(オーケージェー)
特徴
- 世界大手OK Groupの日本法人による運営
- 業界トップクラスの狭いスプレッド
- 高利回りFlash Dealsやステーキングサービス
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料、取引所Maker -0.01%/Taker 0.02%~(キャンペーン時)
- 入金手数料:無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料:400円
- 送金手数料:銘柄により異なる(IOSTは格安)
取扱銘柄:47銘柄 最小購入額:500円 積立サービス:対応 スマホアプリ:高機能アプリあり セキュリティ:コールドウォレット、2段階認証 独自サービス:Flash Deals(年率最大100%超の実績)、マルチチェーン対応 向いているユーザー:スプレッドを重視する方、多様な銘柄に分散投資したい方、レンディングに興味がある方
bitFlyer(ビットフライヤー)
特徴
- ビットコイン取引量9年連続国内No.1
- 創業以来ハッキング被害ゼロの高度なセキュリティ
- 1円から取引可能な初心者に優しい設計
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料、取引所0.01~0.15%(取引量により変動)
- 入金手数料:住信SBIネット銀行無料、その他銀行330円
- 出金手数料:三井住友銀行220円/440円、その他550円/770円
- 送金手数料(BTC):0.0004BTC(XRP、MONA、XLMは無料)
取扱銘柄:38銘柄 最小購入額:1円 積立サービス:対応 レバレッジ取引:bitFlyer Lightningで最大2倍(BTC、ETH対応) セキュリティ:マルチシグ、コールドウォレット、2段階認証 特別サービス:bitFlyer クレカ(利用額の0.5~1.0%がBTCで還元)、ビットコインをもらう、IEO実績 向いているユーザー:少額から始めたい初心者、取引量の多いアクティブトレーダー、レバレッジ取引に興味がある方
 よくある質問(Q&A)
よくある質問(Q&A)
Q1. すでに保有している暗号資産はどうなりますか?
A1. 現時点の案では、既に保有している暗号資産を突然禁止・無効にするような話ではありません。
金商法適用後も保有・売買は可能ですが、
- 取引ルール(情報開示・インサイダー規制 等)が変わる
- 税制が申告分離課税に変わる可能性がある
など、「ルールが変わる」ことによる影響が出てきます。
Q2. 税率20%になるのはいつから?
A2. 2026年度税制改正要望で申告分離課税が正式要望された段階であり、
- 2025年末の税制改正大綱
- 2026年以降の国会審議・法改正
を経て、早くても2026年分の所得から適用されるイメージが多くのメディアで語られています。ただし、これはあくまで見込みであり、確定したスケジュールではありません。
Q3. インサイダー取引に該当するのは誰ですか?
A3. 想定されているのは主に以下のような層です。
- トークンの発行者・開発チーム・財団の関係者
- 暗号資産交換業者の役員・従業員・システム担当
- 上場(取扱開始)・廃止の情報を事前に知り得る業務委託先 など
一般の個人投資家は、未公開の重要情報を職務上知る立場でない限り、インサイダー規制の対象にはなりません。
Q4. 105銘柄以外の暗号資産はどうなりますか?
A4. 報道ベースでは、まずは「国内交換業者が扱う105銘柄」から金商法の枠組みに入れる方針が示されています。
- それ以外の銘柄(海外取引所専用トークン、未上場トークンなど)については、
→ 追加的なルール整備や、将来の制度改正の中で議論されていくとみられます。 - ただし、どこで取引していても「日本の居住者としての申告義務」は変わらない点には注意が必要です。
 関連情報
関連情報
- 金融庁:金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」資料・議事次第(第1〜第5回)
- 業界団体(JVCEA・JCBA等)による税制改正要望書・解説記事(
- Coindesk Japan / CoinPostなどの専門メディアによるWG論点まとめ・解説
 情報源(主な参考)
情報源(主な参考)
- 朝日新聞「暗号資産を金融商品に ビットコインなど105銘柄、税率軽減検討」(2025年11月16日)(朝日・日刊スポーツ)
- CoinDesk Japan「ビットコインなど105銘柄に金商法適用へ、金融庁が方針固める──報道」(Yahoo!ファイナンス配信)(Yahoo!ファイナンス)
- 金融庁:金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」資料・議事次第(第1〜第5回)(金融庁)
- 金融庁「令和8年度税制改正要望(暗号資産取引の分離課税導入等)」(金融庁)
- CoinPost / 各種専門メディアによる税制・インサイダー規制に関する解説記事(CoinPost|仮想通貨ビットコインニュース・投資情報)
 編集後記
編集後記
今回の動きは、
「暗号資産を、従来の金融商品と同等レベルのルールの中に正式に組み込む」
という、日本の暗号資産市場にとって歴史的な転換点になりうるものです。
- 投資家側から見ると
→ 税率引き下げ・損失繰越・インサイダー規制など、メリットが見込まれる部分が多い一方で、 - 業界側から見ると
→ 情報開示・コンプライアンス・体制整備など、短期的には負担増・再編圧力となる可能性も大きいです。
今後は、
- 2025年末の税制改正大綱
- 2026年通常国会での金商法改正案の中身
を注視しつつ、「どのタイミングで・どのルールが施行されるのか」を追いかけることが重要になりそうです。
このページをブックマークしておくと、今後の法改正・税制議論の進展を整理する際のベース資料として活用できます。
The post 【速報】金融庁、暗号資産105銘柄を金融商品に格上げへ【11月16日】 first appeared on CoinChoice(コインチョイス).