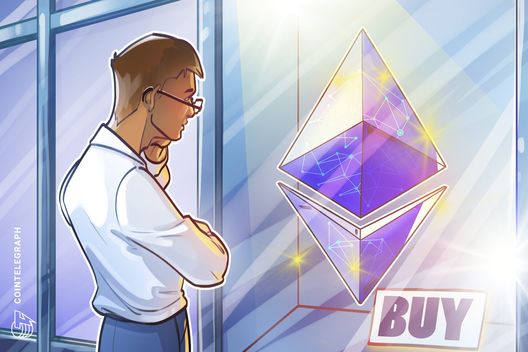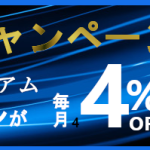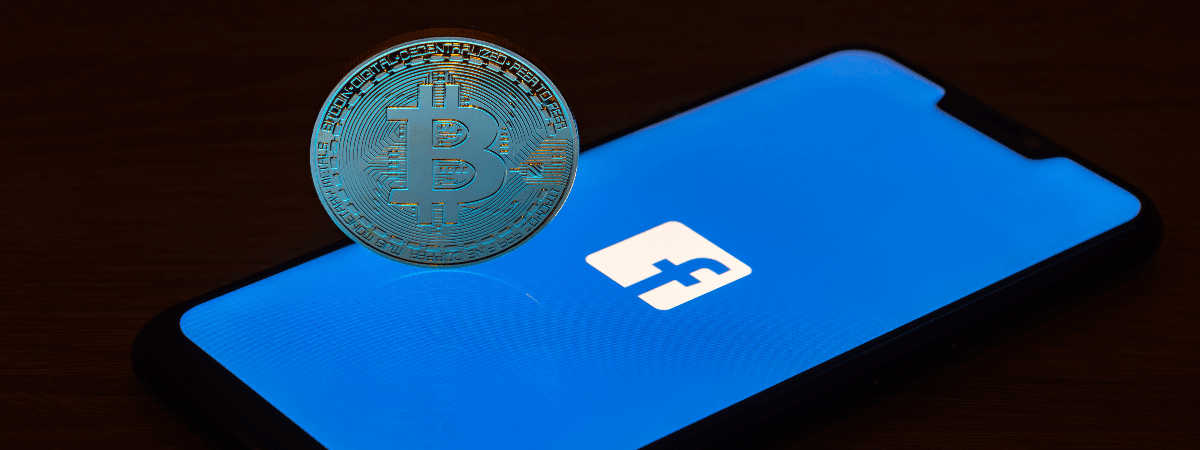

(文:Maki@仮想通貨ママコイナー)
先日、大手SNSのFacebook(フェイスブック)から発表された仮想通貨が話題になっています。
それが「Libra(リブラ)」。

今回は、リブラがどのような仮想通貨なのか、どんな目的で開発されているのか、仕組み・概要を分かりやすく解説していくとともに、フェイスブックという誰もが知る企業が仮想通貨を作るという意味について、考えてみましょう。
Libra(リブラ)とはどんな仮想通貨?

Facebookが6月18日に発表した、Libra(リブラ)の存在。ホワイトペーパーやテストネットの公開も併せて行われ、海外はもちろん日本でも大きな注目を集めています。リブラのホワイトペーパーより、概要をまとめてみましょう。
Libra(リブラ)が生まれた理由
リブラが目指しているのは「多くの人に力を与える、シンプルで国境のないグローバルな通貨と金融インフラになること」だそう。ビットコインをはじめとした仮想通貨は、国境がなく世界中でやり取りができる電子的な通貨として知られていますが、リブラも同じように海を越えて世界中で利用できる通貨として、また金融の土台になるべく開発を進めているとのこと。
人々が金融サービスを受けるにあたり、貧しい人ほど高い手数料など多くのお金を払っている現状を、リブラは危惧しています。

仮想通貨やブロックチェーン技術は国境を越えて広く使われること、クレジットカードや銀行のキャッシュカードを持たずとも、スマートフォンひとつあれば送金がすぐにできることをあげていますが、既存のブロックチェーンシステムはまだ主流になっているとは言えませんよね。
仮想通貨の問題点として、
- 価格の乱高下
- スケーラビリティ問題(送金詰まり)
- 仕組みが理解しづらい
- そもそも使いづらい
- マネーロンダリング(資金洗浄)のおそれ
- 規制が国や地域によってバラバラ
といったことがあげられます。
そこでリブラは、もっと多くの人が金融サービスを安く受けられること、オープンかつ瞬時に資金を移動できるようになれば、世界中で経済機会が生まれ、活発な取引が行われるようになると考えました。多くの人が持つスマホで資産を管理したり送金を行う場合、その仕組みはシンプルであり、誰もが利用できるよう簡単なものでなければ使われません。
この考えから誕生したのが、Libra(リブラ)です。
Libra協会の存在

フェイスブックから発表されたLibraですが、その裏には「Libra協会」という存在があります。これは独立・非営利・メンバー制の組織で、本部はスイスのジュネーブにあります。リブラが実際に稼働した後、フェイスブックが主体となるこの協会が運営をしていくとのこと。
協会メンバーの一例はこちら。
- MasterCard
- PayPal
- Visa
- eBay
- Coinbase
決済・ブロックチェーン・テクノロジー・ベンチャーキャピタル(投資会社)といった各ジャンルに知名度の高い企業がそれぞれ参加していますね。現時点ではフェイスブックが主導という形ですが、最終的な意思決定の権限はLibra協会にあり、フェイスブックは今後もリブラをベースにしたサービスを開発していくといいます。
この顔ぶれからも、世界から注目される理由として納得できるでしょう。
リブラの仕組みと特徴「安全・対応力・柔軟性」

続いては、リブラの中身について見てみましょう。
リブラはイーサリアムをベースにして開発されたチェーンなどではなく、オリジナルの独自ブロックチェーンとなっており、その特徴はこちら。
- 数十億のアカウントに広く対応できる、スケーラビリティ性
- 資産や財務情報の安全性を守る、高いセキュリティ性
- 金融サービスの拡大を進めるための、柔軟性
これらを実現するために、リブラのブロックチェーンでは次のことが取り入れられています。
- プログラミング言語は「Move」
- 合意の方法はビザンチンフォールトトレランス(BFT)アルゴリズム
- 最初はコンソーシアムチェーン、将来的にはパブリックチェーンでの運用
ビットコインをはじめとした多くのブロックチェーンは「パブリックブロックチェーン」と言い、第三者が取引に関する情報を閲覧することができ、その透明性が知られています。
対してリブラのブロックチェーンは「コンソーシアムブロックチェーン」と言い、信頼できるいくつかの企業や団体によって取引の合意が行われる仕組みになっています。

将来的にはビットコインのように第三者も取引に関する情報を閲覧できるよう、パブリックブロックチェーンとして稼働させることを目標としていますが、現在のところは数十億の人の取引をサポートするにあたり、スケーラビリティ問題(送金詰まり)や安定性の課題があるため、当面はコンソーシアムチェーンとして機能するとのこと。
リブラブロックチェーンがローンチされて5年以内に、パブリックブロックチェーンとして移行できるよう取り組んでいくそうです。
ビザンチンフォールトトレランス(BFT)について
リブラで取引の合意として用いられるのが「ビザンチンフォールトトレランス(BFT)」というアルゴリズム(仕組み)。悪意あるユーザーのせいで意見がまとまらず、合意形成に失敗してしまうことをビザンチン将軍問題といいます。

このビザンチン将軍問題がもし発生したとしても、システム全体としては滞りなく稼働することを「ビザンチンフォールトトレランス性がある」と言います。リブラでは、協会に参加しているメンバーがノードとして機能し、取引に係る合意形成を行います。
ビットコインの取引合意には「Proof of Work(プルーフオブワーク)」という仕組みが用いられていますが、こちらはコンピューターによる電力消費が激しいことからエネルギー効率が低く、さらにいくつかのブロック生成を重ねるまで取引が完了したとみなされない(ファイナリティ)こともあり、BFTは大きなメリットがある合意方法だと言えます。
リブラリザーブとは
ビットコインやイーサリアムといった仮想通貨はかなり知名度が高くなり、決済や取引、投機(投資)として使用されるようになりました。しかし、多くは基盤となる「裏付け」の資産がありません。つまり「ビットコインやイーサリアムの価値はどこから来ているの?」という状態になっています。
そのため、現状では多くのユースケースが投機(投資)となり、もともとデジタル通貨として設計されたはずのビットコインは大きく価格が上下するように……。

「数十億の人に向けて広く使われる存在に」と考えているリブラは、これほど価格が大きく動いている仮想通貨は敬遠されると考え、価格が安定する通貨になるように設計を行いました。それが、リブラリザーブ(リザーブ=貯え)です。
法定通貨と等価となるリブラを購入したユーザーは、その法定通貨をリザーブに移します。リブラコインが作られれば作られるほど、リザーブの資金も貯まっていくということですね。
リザーブに貯まった資金ですが、これはリスクの低い資産に投資され、少しずつではありますが利子を発生させることで、この収入がリブラの発展やリブラ協会の運営に使われていきます。
ただ、リザーブ資金がどこに使われたのか?横領の恐れは?というカウンターパーティリスクを抑えるため、信用できるカストディ(保管)機関で構成されたネットワークに、分散されて保管されるとのことです。もちろん、リザーブ資産に対しては徹底的な監視が行われ、透明性を確保していきます。
リブラバスケットとリブラの価値

リブラコインは、コイン発行時にユーザーがリザーブする法定通貨のほか、そのリザーブを使って、各国で安定、かつ信用度の高い公債や通貨といったボラティリティ(値動き)の低い資産に投資を行ったものが、価値の裏付けとなります。
つまり、ユーザーの法定通貨と、リザーブを使って投資した公債といった資産を一緒くたにした「バスケット」に価値が結び付けられます。(複数の銘柄をまとめて売買するパッケージ取引をイメージしてみてください)
もちろん、リブラの価値がまったく変動しないということはありませんが、経済危機など大きな問題が起こったときにも影響を受けにくいような設計になっているということです。
言い換えれば、リブラの価値は各国の法定通貨のほか、公債といったリスクの低い資産によって成り立ち、さらに安定した価値をもつ国の信用(資産)の上に成り立っているとも言えるでしょう。
また、ユーザーがリブラを売買したり法定通貨に交換したい場合、リブラ協会に認定された業者(機関)のみが法定通貨とリブラのリザーブを出し入れできるようになっているため、ユーザーはこの認定業者を利用することでリブラの売買を行うことができます。
Libra(リブラ)が発表、注目される最大の理由

リブラについて発表されてからまだ日が浅い一方、世界中で注目されていることが分かります。フェイスブックという、誰もが知る企業から独自ブロックチェーンが開発され、そこで取引を行うことができる仮想通貨が発表されたというのが、今回の最大の見どころです。
これまでビットコインやイーサリアム、リップル、ライトコインといったさまざまな仮想通貨プロジェクトが誕生し、現在まで成長を遂げています。日本でもブロックチェーン技術を取り入れる企業が増えており、着実に仮想通貨・ブロックチェーンの波が起こっていますよね。
しかし、それはあくまで企業単位でのことですし、個人であっても実際に仮想通貨に触れるのはごくごく一部の人のみ。さらにハッキングやマネーロンダリング、詐欺といったマイナスイメージがあることで、仮想通貨の難しい仕組みが余計に広がりにくくなっています。

ここで今回登場したのが、世界で老若男女問わず利用者の多いフェイスブック。当然、一般のニュース番組でも取り上げられますし、認知されるスピードもこれまでのプロジェクトとは段違いでしょう。
そして、リブラは主に私たち一般ユーザーを取り込もうとしており、その地盤としてマスターカードやペイパル、ビザ、ウーバーといった、膨大な顧客を抱える協会メンバーを味方につけています。
いくらリブラが魅力的で、送金もこれまでの仮想通貨と違って簡単!とは言っても、使える場所(ネットワーク)がなくては意味がありません。リブラはまずフェイスブック、そしてマスターカードやビザといった膨大な顧客のネットワークがあるため、その課題をクリアしていますよね。これは、今後爆発的に仮想通貨(ブロックチェーン技術)を広めるための準備ができたと言えるでしょう。
ウォレット「カリブラ(Calibra)」の発表と期待

実際に、ホワイトペーパーが発表されてからテストネット(お試し版)もすでに公開されており、さらにリブラを簡単に送金できる「カリブラ(Calibra)」というウォレットについても、来年リリースすると発表しています。
テンポ良く段階的に発表を行っていることで、私たちユーザーに向けて「使いやすそうだな」という意識を埋め込むほか、リブラは将来的に電車など公共交通機関で利用できたり、店舗での少額決済ができたりといった具体的なユースケースについても周知させ、期待感を上げています。
もちろん、リブラが念頭に置いているセキュリティの面でも万全を期しています。
セキュリティについては、まず万が一不正利用が行われたときの補償のほか、ウォレットを利用するスマートフォンなど端末をなくしてしまったときにも専門のサポート体制があり、銀行やクレジットカードを利用するときのように厳しい個人情報の取り扱いを行うとしています。
賛否両論?リブラの今後について

リブラが発表された後に飛び出したニュースが「開発停止を求める」という驚きの話題。
アメリカ下院金融委員会が、フェイスブックが起こしている過去のトラブルを考慮し、議会や規制当局が内容を精査するまではリブラの停止を、と求めていることが分かりました。
世界中に数十億のユーザーを抱えるフェイスブックですが、実は過去にそのデータが流出したり、プライバシー保護を怠ってきたことが知られています。そのため、今後リブラ側(フェイスブック)がどのように対応していくか注視していく必要があります。
また、リブラのホワイトペーパーを読み、有識者からはさまざまな声が。
- これと言って突出した部分がない
- アルゴリズムは良い
- 期待外れだった
- 方針が良い
当然のことながら賛否両論あります。
プロジェクトの中身はもちろんですが、こうした大手企業が「仮想通貨を新たに発行する」ということが、大きな意味を持ちます。この流れに続く企業が現れることも十分考えられますし、仮想通貨の普及に向けた大きな一歩だと言えますね。

2020年のローンチを目指し、今後リブラのネットワークに参加する企業も100社ほど募集するとのこと。今以上に巨大なネットワークを作り、大きな注目を集めていくであろうリブラ。現在の課題をどう乗り越え、実際に使われていくのか見ものです。
【こんな記事も読まれています】
・Facebbokの仮想通貨リブラ(Libra)の開発停止求める、米国下院金融サービス委員会が声明発表
・Facebookの仮想通貨リブラ(Libra)、グローバル企業vs国家の観点で考察する
・Facebookのステーブルコインプロジェクトに関わる6つの未来予測
筆者も講師陣として活動をしている有料プライベートグループ「Cryptolabo(クリプトラボ)」では、初心者・中級者~ともに仮想通貨トレーダーとして幅広く知見を広げられるよう随時ボイスチャット・情報配信等を行っています。ぜひご活用ください。
▼Cryptolabo
https://www.izizlabo.net/