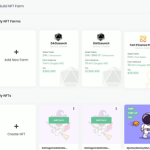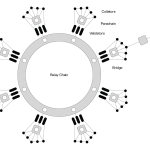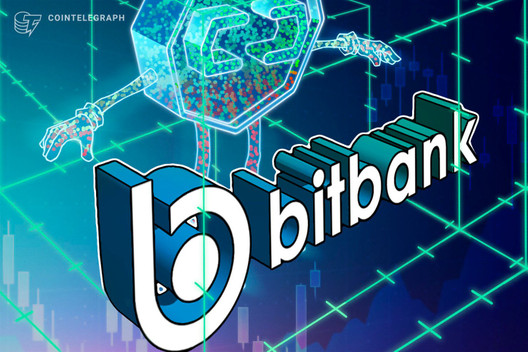10月30日にテレグラム(Telegram)の分散型金融(DeFi)に関する日本コミュニティグループでAMA(Ask Me Anything)のイベントが開催されました。HashHubの平野がゲストとして回答側に立ち、イベント参加者からDeFiに関する質問に答えました。
DeFiに関するさまざまな質問が集まり、DeFiプロジェクトのマネタイズやDeFi上にどのようなアセットが取り込まれるかなど、鋭い質問も多く集まりました。今回は、当日の質問からいくつかピックアップして紹介していきます。
DeFiは今後一般の人にどのように影響しますか?
最初の質問は、「DeFiは今後一般の人にどのように影響するか?」というものです。これについて、そもそも一般の人は、まだ暗号通貨を持っていないので、少し先が長いのではないかと見解が示されました。その状態を抜け出すには、DeFiが一般の人に対してもメリットを提示できるようにならないといけないとも回答されています。
例えば、高金利でお得であるという簡単な考えでもよく、他にもさまざまな国の株価や金融商品と連動するトークンであるシンセティック・アセット(Synthetic Asset)が簡単に買えるなど、既存のものより便利であることを示せない限り、一般への普及はないとのことでした。Synthetic Assetは利便性の提示になり得ると考えられており、既存の仕組みでは、外国株式や他国のアセットを購入するのに多くの手続きが必要になります。
DeFiはそういった煩雑さを取り除ける可能性があります。いずれにしても、広く使われることを目指すのならば、分散性や第三者を信頼する必要がないといった理由以外にも利便性の提示が必要です。
DeFiにブロックチェーン外からの価値を持ち込むのに適切な方法は?
次の質問は、「現在のDeFiプロダクトは、ほぼ暗号通貨関連のみのアセットを取り扱っており、閉じていたエコシステムを徐々に拡大しているフェーズだと思います。ブロックチェーン外からの価値を持ち込める可能性があるとすれば、どんな方法がありそうですか?」というものです。
これに対して、一番簡単な方法は、やはりSynthetic Assetだろうとの回答でした。DeFiのエコシステム上で最も使用されているステーブルコインのダイ(DAI)もドルに裏付けされているわけではなく、ドルに連動するSynthetic Assetだと言えるでしょう。オラクルやインセンティブ設計が必要ですが、このようなアセットをブロックチェーン上で構築することは、DeFiにブロックチェーン外からの価値を持ち込むのに適切な方法の一つでしょう。
例えば、アセット自体がアップル(Apple)の株に裏付けされていなくても、その株価と連動するトークンで満足できる人はいます。これにはカストディも必要なく、遥かに先の未来だとの見解でした。現物に裏付けされているアセットが今後出てくるとしても、株価に連動されたミラーリング資産の方が早いでしょう。既にシンセティックス(Synthetix)やユニバーサル・マーケット・アクセス(UMA)といったプロジェクトが存在します。
株と連動するトークンの場合長期的な保有のリスクは考えられますか?
次の質問は、Synthetic Assetの長期保有のリスクについてです。回答としては、普通に現物株式を保有するよりは、Synthetic Assetのほうがリスクは高いだろうという意見でした。そもそも実際に株を買っているわけではないため株主名簿に記載されず、スマートコントラクトのバグや、イーサリアム(Ethereum)自体が抱えるリスクなど、株を通常に取引する場合には発生しないリスクを負うことになります。加えて、そのリスクを負うことでリターンが大きくなることもありません。
将来的には安心してSynthetic Assetを持てれば良いとしつつも、まだエコシステムはそこまで成長してない点にも言及されていました。長期的な保有をするなら、これまで通りに株の現物を購入した方が安全と考えられています。
DeFiプロジェクトはどうやってマネタイズをすべきですか?
この質問に対しては、実際に利益を生み出せているDeFiのプロジェクトは、今のところメイカーダオ(MakerDAO)だろうとの回答でした。これは独自トークンであるMKRの価格上昇を通してという意味を含んでいます。その点で、少なくともDeFiを構成する一番下にある段階の勝ち筋はMaker DAOが既に証明したと言えます。
しかしながら、DeFiの一つ上の段階にあるインスタダップ(instadapp)のようなアプリケーション層は、ビジネスモデルの実証に至っていません。コントラクトウォレット経由で手数料を徴収したりと、方法論はあるものの、まだ証明されていない状況です。何%の手数料を徴収し、どのくらいのアクティブユーザーを集めれば利益を生み出せるといった逆算は可能ですが、簡単ではないでしょう。
ビットコインはイーサリアム上での拡大が必要か
最後の質問は、ビットコイン(BTC)のイーサリアムチェーン上における拡大をどのように予想しているか?という質問です。
平野は個人的にラップド・ビットコイン(WBTC)は保持していないとのことでしたが、もし持つとしたら、ブロックファイ(BlockFi)などよりも金利がつくようになったときだと思うと回答をしました。そうなったときはWBTCはDeFiのレンディングで貸し出されるようになるかもしれないと付け加えています。
実現のためには、DeFiのエコシステム上で、分散型取引所(DEX)でのWBTCを用いたペア通貨数やレバレッジ取引の出来高が多くならないと金利は高くなりません。WBTCのようなカストディ型でもトラストレスな形式でも、どちらにしても同じですが、イーサリアム上でBTCを使いたいという動機が必要で、現段階においてはまだ希薄であると言えます。
さまざまな情報をAMAで入手
DeFi Japanのテレグラムは、分散型金融について語る日本のコミュニティです。このようなAMAイベントもゲストを呼んで不定期で開催されているので、興味を持った人は是非テレグラムグループに参加してみてはいかがでしょうか。
>>チャンネル参加リンク:https://t.me/Defi_JP
【こんな記事も読まれています】
・コンセンシス(ConsenSys)がリリースをした金融企業向けツールCodefiとは?
・DeFi(分散型金融)のセクターそのものに投資をする合理的な回答はETH?
・ステーブルコインとDeFi(分散型金融)におけるレンディングの金利はなぜ高いのか?
d10n Labのリサーチコミュニティでは、ブロックチェーン業界の動向解説から、更に深いビジネス分析、技術解説、その他多くの考察やレポート配信を月に20本以上の頻度で行なっています。コミュニティでは議論も行えるようにしており、ブロックチェーン領域に積極的な大企業・スタートアップ、個人の多くに利用頂いています。
▼d10n lab 未来を思考するための離合集散的コミュニティ
https://d10nlab.com