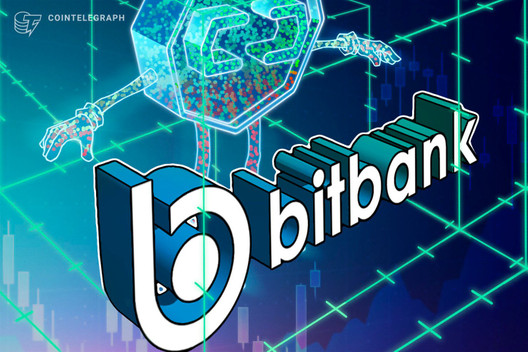日本人の寿命は世界と比べて長いというデータがあります。
現在65歳の人の平均余命は男性で19.55年、女性で24.38年となっており、半分以上の人がすでに老後を20年以上過ごすことが分かっています。
そして、今後は医療技術などの発達で寿命はさらに延びていきます。
そんな中で心配になるのは老後資金です。
少子高齢化が進んでいて、今現役世代の人たちが老後になった時に年金が十分もらえるか分からない状況になっています。
なので、現役世代から堅実に老後資金を作っていく必要があります。
今回は老後資金を作る上で便利な「iDeCo」という制度について解説します。
加えて、iDeCoを申し込む金融機関はどのように選べば良いかについて比較していきましょう。
iDeCo(イデコ)とは?メリットやデメリット、手数料、節税の方法、おすすめ商品を紹介!
メリット多数!iDeCo(イデコ)とは?

iDeCoの正式名称は「個人型確定拠出年金」です。
簡単に言うと、自分で掛け金を拠出して自主的に運用して老後の資産を作る制度です。
公的年金制度とは別で、公的年金だけでは足りない老後資金を賄うためにとても有利な仕組みになっています。
iDeCoは原則20~60歳未満の人が任意で加入することができます。
一度、iDeCoを申請して掛け金を拠出し始めると基本的には60歳以降にならないと資産を引き出すことができません。
もし現状の家計が厳しいようであれば無理してiDeCoを始めるのはリスクが伴うので注意しましょう。
iDeCoでは加入者が任意で掛け金を拠出していくことができます。
ただ、加入者の国民年金の被保険者種別や会社員の人の企業型確定拠出年金や企業年金の加入状況によって掛け金の上限額が決まっています。
しっかりと上限額を把握して、自分の都合に合う額を拠出していきましょう。
iDeCo(イデコ)のメリット

iDeCoは老後資金を作りやすくするための制度です。
なので、そのためにたくさんのメリットがあります。
ここではiDeCoの大きなメリットを以下に3つ説明します。
「所得控除」で納めた税金が戻ってくる
iDeCoでは掛け金として拠出した金額の全額が「所得控除」となります。
このメリットがあることで、老後だけでなく現役世代の時でも節税をすることができるため生活を少し楽にすることができます。
会社員の人で掛け金を事業主払込として給与天引きにしていると年末調整によって所得控除がされます。
この場合は会社員の人は特にやることはありません。
しかし、年末調整ができなかった人や会社員以外の人は別で年末調整の申請や確定申告をしなければいけません。
iDeCoで得た利益には税金がかからない
iDeCoは掛け金を拠出したら、それを自分の判断で運用をします。
そして、運用によって利益が出た場合はその全額を受け取ることができます。
株式・債券などの一般的な金融商品で運用をして利益が出た場合は基本的に約20%の税金がかかります。
その税金が無いだけで節税効果は非常に大きくなります。
運用資産を受け取るときも節税できる
iDeCoで60歳以降になると運用資産を受け取れるようになります。
その際には「年金方式」か「一時金方式」かその両方を選ぶことができます。
年金方式は運用資産を引き出す頻度をあらかじめ決めてその度に定期的に資産を受け取ります。
その時に受け取った金額が「公的年金等控除」として控除されます。
一時金方式は運用資産を一括で受け取る方式です。
その時に受け取った金額が「退職所得控除」として控除されます。
iDeCo(イデコ)証券会社の選び方

iDeCoを始めるにあたって証券会社選びは非常に重要です。
一度、証券会社にiDeCoを申し込んでしまうとそれ以降別の証券会社に移管する時には手数料が発生してしまいます。
なので、60歳までiDeCoをするにあたって満足のいく証券会社を選びましょう。
ここではそんな証券会社の比較のポイント3点を説明していきます。
手数料が安い
iDeCoをしていると口座管理手数料がかかります。
これは各証券会社によって金額が異なるので、迷っている場合はこの金額が少しでも安い会社を選びましょう。
現在では口座管理手数料を無料にしている証券会社が多くなっているので、そういった証券会社を選ぶのもおすすめです。
運用商品のラインナップ
iDeCoを取り扱っている証券会社によって購入できる運用商品の数や種類に違いがあります。
あまり投資の知識が少ない人は商品数が少なめの証券会社を選ぶと選択肢が狭まり選びやすくなるでしょう。
逆に豊富な選択肢から吟味して選びたい人は商品数の多い証券会社を選びましょう。
サポート体制や使いやすさ
iDeCoは60歳まで運用資産を引き出せない上に老後資金のための資産という重要度の高いものとなります。
その場合、iDeCoの制度や運用についてのサポートやiDeCoのサイトの使いやすさが大事になってきます。
初心者でも満足のいくようiDeCoを使いこなしやすい証券会社を選ぶ必要があります。
iDeCo(イデコ)を比較!おすすめ5選

iDeCoを取り扱っている金融機関はとても多くあります。
ここでは数ある証券会社からiDeCoを申し込むにあたっておすすめの5つの証券会社のメリットや特徴を紹介していきます。
楽天証券
は口座管理手数料が無料で、商品数も十分にあるためおすすめの証券会社です。
また、資産管理画面がとても見やすくあまり機械に慣れていない人でも操作しやすいです。
セミナーやサポートもあるので初心者でも安心して使えます。
- 加入時の手数料(初期費用):2,777円
- 口座管理手数料(月額):167円
- 還付手数料:1,461円/1回
- 給付時の手数料:432円/1回
- 投資信託の数(種類):32本(国内外の株式・債券、REIT、コモディティなど)
マネックス証券
マネックス証券は口座管理手数料が安いだけでなく、iDeCo専用のロボアドバイザーが資産配分を提案してくれます。
加えて、マネックス証券のiDeCoはお客様満足度が94.5%と高く、安心して使えることが特長です。
- 加入時の手数料(初期費用): 2,777円
- 口座管理手数料(月額):167円
- 還付手数料:1,461円/1回
- 給付時の手数料:432円/1回
- 投資信託の数(種類):24本(国内外の株式、債券、REIT、ゴールドなど)
松井証券
松井証券のiDeCoは運営管理手数料が無料で、商品数は12本と少なめに用意されています。
選ばれている12商品は厳選されているものなのであまり商品選びで悩みたくない人におすすめです。
また、松井証券は創業から100年以上の歴史があるためそこで積み上げたノウハウがあり、非常に安心感があります。
- 加入時の手数料(初期費用): 2,777円
- 口座管理手数料(月額):167円
- 還付手数料:1,461円/1回
- 給付時の手数料:432円/1回
- 投資信託の数(種類):12本(国内外の株式、債券、REIT、コモディティなど)
SBI証券
SBI証券のiDeCoは運営管理手数料が無料で、取扱商品数が今のところ83本と圧倒的に多いです。
あらゆる商品から吟味して投資をしていきたい人におすすめです。
ただ、SBI証券は2023年までにiDeCoで運用できる商品数を35本以下にするとしています。
商品数は少なくなりますが、より厳選された商品が残り運用に失敗するリスクをさらに引き下げることができます。
- 加入時の手数料(初期費用): 2,777円
- 口座管理手数料(月額):167円
- 還付手数料:2,109円/1回
- 給付時の手数料:432円/1回
- 投資信託の数(種類):83本(国内外の株式、債券、REIT、コモディティなど)
岡三オンライン証券
岡三オンライン証券のiDeCoは運営管理手数料が205円かかってしまいますが、岡三オンライン証券のiDeCoでは提供しているファンドナビで最適なポートフォリオを組んでくれます。
これによって初心者でもiDeCoを使った投資を簡単に始めることができます。
- 加入時の手数料(初期費用): 2,777円
- 口座管理手数料(月額):372円
- 還付手数料:1,461円/1回
- 給付時の手数料:432円/1回
- 投資信託の数(種類):41本(国内外の株式、債券など)
比較して自分に合ったiDeCo(イデコ)を始めよう

ここまででiDeCoという制度について、そのメリットについて説明してきました。
そして、証券会社の選び方とおすすめの証券会社を紹介してきました。
iDeCoは老後資金を作るための自分の年金制度で、様々な場面で節税ができます。
こういったメリットを活かして、効率良く老後資金を作っていきましょう。
そして、iDeCoを始めるには証券会社で口座開設をしなければいけません。
証券会社は手数料が安さと商品数とサポート体制が充実しているかどうかで選びましょう。
商品数は人によって好みはありますが、しっかりと自分に合う証券会社を探して口座開設をしましょう。
今回紹介した証券会社はどれもおすすめなので、ぜひ検討してみてください。