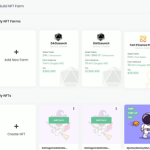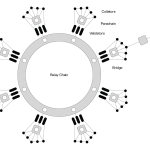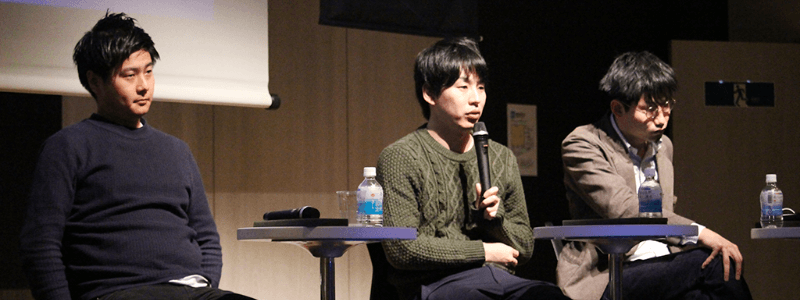
 (左から:大日方祐介氏、福島良典氏、平野淳也氏)
(左から:大日方祐介氏、福島良典氏、平野淳也氏)
2018年12月18日に、MicrosoftとNutrinoとHashHubの3社共催で、「ブロックチェーン・ビジネスサミット ~Beyond PoC~」が開催されました。
本コラムでは、下記のメンバーが登壇しブロックチェーンの次のユースケースをテーマにしたパネルディスカッションを紹介します。
- 大日方祐介氏
- 福島良典氏(株式会社LayerX CEO)
- 平野淳也氏(株式会社HashHub 共同創業者)
- 柿澤仁氏 (OmiseGo)/モデレータ
国内を代表するブロックチェーンプレイヤーたち
柿澤:私は、OmiseGoという会社でビジネスデベロップメントをしています。まず、パネラーの皆様に一言ずつ自己紹介をお願いします。
大日方:僕はもともとイーストベンチャーズで働いていて、当時投資のミーティングにいらしたbitFlyerの加納さんから話を聞いて興味をもつようになりました。
CryptoAgeという若い人にフォーカスを当てたコミュニティをやっています。海外から最前線で活動されている人を呼んでミートアップをしたり、最近ですとNodeTokyoというカンファレンスイベントを開催したりといったことを行っています。
福島:今、LayerXというブロックチェーンを技術的にコンサルティングする会社をやっています。世間ではブロックチェーンは投機などのイメージがありますが、僕らは証券電力不動産といった領域に使える、コスト削減をできる技術と考えています。
そういったところに関心があるお客様や海外のプロジェクトと案件をやったりしています。何か皆さんのビジネスのヒントになることを話せればと思います。
平野:こんにちは平野です。今回、マイクロソフトさんとNeutrinoさんと共同主催させていただいているHashHub創業者です。ブロックチェーンスタジオというものをやっています。いろいろなことをやっているのですが、ブロックチェーンに関することはなんでもご相談ください。
もう少し説明すると、起業家エンジニア向けにコワーキングスペースでコミュニティを作ったり、企業向けのコンサルティングしたり、エンジニア向けの講座を行ったりレポートを作成したりしています。ネクストユースケースということでコンソーシアムチェーンやプライベートチェーンの話がされていたと思うので未来感のある話ができればと思っています。
信用コストが下がったことによって出てきた新しい金融のビジネスレイヤー
柿澤:ありがとうございます。ずばりネクストユースケースは何になると思いますか?いろいろレポートを書かれている平野さんお願いできますか?
平野:今日ずっと話していたのは信用コストを下げるところ、さんざん話をされているので余り必要なさそうですが、ID管理や貿易などのトランザクションをもうちょっと透明性のあるものにできます。そういったものは当然あります。
他に今日のカンファレンスではこれまであまり話されていなさそうなのは、今、イーサリアム上で「分散型金融」というものがあります。要は銀行とか証券会社に頼らずアセットが交換できる0xプロトコルなんてものがあったり、ドル建てのステーブルコインが銀行預金を担保にしていないが暗号通貨を担保に実現可能になったりしているMakerDAOといった経済圏が徐々に出てきています。
こういったものがすぐに現実社会に影響力がある経済規模になるかというと、そうは簡単にいかないのですが、すごく面白い動きです。

柿澤:福島さんは、ネクストユースケースという点では、いかがでしょうか?
福島:フィンテックの中のブロックチェーンとかのほうが皆さん刺さりやすいのではないでしょうか。今フィンテックで何が起きているかと言うと、銀行のアンバンドリング、証券会社のアンバンドリングがまさに起きています。
分かりやすい例として、決算書を見て融資するかどうかを決めていたと思いますが、決済サービス事業者が決済情報を持っていて、与信をしています。いろいろな事業者に与信が分散している流れと言えます。
ブロックチェーンがどう関わっているかと言うと、1つの会社がその与信リスクを取って貸し出しています。そこでブロックチェーンで分散化や、トークンとかで小口化できないかなどをユースケースとして考えていることはあります。
ブロックチェーンの最初のユースケースはビットコインです。すごいところはいろいろありますが、一つは自分が持っている量を疑ったことがありますか?何BTC持っているというときに、自分でノード立てて確認することもできますが、そこに出ている量を疑ったことって無いですよね。これはすごいことですよね。
ここで、そのトークンを持っていることをどう担保されているのか、誰かの信頼、信用を使わずに証明できるところがポイントだと思っています。
これからいろいろなものが証券化される、そのときその権利を証券化したときに、権利の補償を誰がするのかがすごく問われることになると思うんですよね。
ゲームのアイテムがトークンになったとき誰が持っているのか、ファクタリングの債権を作った時にその債権を誰が持っているのか、グリーン電力が証券化されたとき、トレーサビリティはどう担保されるのか。こういったところにブロックチェーンは使われ、金融的なビジネスになるのかと思っています。
“アセットの所有権が証明されている”ということはブロックチェーンが達成した偉業
柿澤:権利を表す、所有権を表すことはすごいことだという話があったと思っていて、あまりブロックチェーンに対して評価されていないところかなと思いますが、そこをもう少し詳しくお伺いしていいですか?
福島:ブロックチェーンは台帳、帳簿なんですね。何を書いてもいいが、資産を表すようなもの、誰がいくら持っているか、イーサリアム上にあるトークン、自分が何トークン持っているかが、台帳に書いてある。
自分のPCでも書けるじゃないかと思われるかもしれませんが、ブロックチェーンの巧みなところは同じデータを世界中のPCが持つことで合意していることです。マイニングやステーキングを持ち込むことで一つの状態に収束することが出来たということです。
世界中で共有された台帳を作ることができたことが画期的なんです。
シンガポールで誰も知らない人がICOをやって、僕がトークンを買ったとして、例えば20%僕がその権利を持っているということは保証されますよね。
そのプロジェクトが進むかどうかは信用しなくてはならないですが、20%の権利を持っていることは台帳上で補償されているというのは、すごくブロックチェーンが達成した大きな進歩なのではないかと思います。
スマートコントラクトというのが、バズワードのように言われているが、日本語だとスマートな契約などと翻訳されて、契約というと書類上の契約、企業間の契約業務のように思われるかもしれないが、そういう契約ではないんですよね。
台帳の中の数字を書き換えるルールを記述したものがスマートコントラクトです。送金する時も、XX%の株式を持った人にこういう配当を配るということがスマートコントラクトで記述できます。
契約業務がなくなるというのはというのは嘘だと思っています。権利の移転をプログラマブルに、1対1の送金のような単純なもの以外に、2人が署名したら送金できるというような複雑なルールを記述するのに向いています。
一番コアにあるのは、みんなに共有されているデータは、より信用を持つということかなと最近は思ってます。

オープンソースの活用のモデルからブロックチェーン業界には学ぶヒントが
柿澤:ビジネスに適用する際の、フィジビリティ考えてるの?みたいなところ多いですよね。この辺、平野さんが、やっているd10n Labを見ていると、興味深いことが多く書かれているなと思ってます。
最近は従来のオープンソースの活用方法、ビジネスモデルからブロックチェーン業界が学ぶべきことは多いよね、なんて話もしていましたよね。この点についてお聞かせ頂きたいです。
平野:オープンソースソフトウェアの周りにあるエコシステムやその周りにあるビジネス構造はブロックチェーンの人たちは勉強すべきだと思っています。
というのも、ブロックチェーン周りの技術はだいたいオープンソースソフトウェアだからです。ソーシャルコストを削減する技術がクローズドだったら成り立たないですよね。ウォレットも秘密鍵を保管してもクローズドコードが中にあったらサービス運営者が秘密鍵盗めますよね。ということで、とにかくいろいろープンソースソフトウェアになっている。思想的にでもですね。
そうすると、従来的なオープンソースソフトウェアの世界から学ぶことはいろいろあるはずなんですね。例えば、オープンソースソフトウェアを使ってビジネスをしているところで、代表的なRedHatがあります。彼らは、オープンソースのLinuxをいろんな企業に導入しています。
世界中からコントリビュートがいるLinuxですが、Githubのコードにあるものを各企業が自分でビルドして利用をするのは難しいですよね。そこで、RedHatが導入と業界ごとの適切なサポートをして、アップデートがあれば保証するということをやってます。
じゃあ、このモデルをブロックチェーン領域でやろうとしているところはどこか?IBMがやっているHyperLedger Fabricとかは近いですよね。HyperLedger Fabricはコンソーシアムブロックチェーンなどを構築するためのオープンソースソフトウェアです。
IBMはこれをオープンにしながら、その導入支援やコンサルティングでビジネスにしようとしています。Red HatとLinuxの関係と同じですよね。こういったオープンソースの活用事例は、最近レポート出したので、興味ある方はd10n Labで見てください。
自分の会社の事例も紹介させていただくと、最近リリースしたものですがLightning Networkを使ってマイクロペイメントのやり取りができる製品をリリースしましたLightning Network自体は世界中からコントリビュートされるプロジェクトです。0.01円とかを送金できる双方向のペイメントチャネルです。
でも相手にInvoiceという請求書を発行してもらわないといけない。そこをなめらかにするSaaSめいたものを開発しています。ビジネスとしての活用方法はいろいろあると考えているのですが、例えば、5分間サービスを使ってくれたらリワードとして裏側で5円送るというような事ができたり、アイデア次第でいろいろなものができます。これも活用したいという企業がいましたらお問い合わせください。
参考:ightning Network上で誰でも簡単にマイクロペイメントを受け取れる Denryu System βリリースのお知らせ
柿澤:オープンソース・ソフトウェアをどうぞ使ってくださいってハードルが高いということですよね。個人的に仰っていることは分かります。その辺りについて福島さんは開発されていた経験からするとありだと思いますか?」
福島:ありだと思いますね、かなりリテラシーが高くないとオープンソースソフトウェアは使えないと思うので。あくまで技術は技術ですから。
僕は、よく”どのレイヤーでビジネスをしているのですか?”という話をするのですが、ブロックチェーンに足りないのはエコシステム、それを活用してお金を稼げている会社がいないんです。ブロックチェーンは、データベースとしての性能は良くないので、複数の会社さんが載って初めて意味のある仕組みになるんです。全てに共通しているのは一社に閉じたら意味がありません。
複数の利害関係者が絡んだときにソーシャルコストが従来、発生しています。ブロックチェーンは、そこを下げていく技術です。載ってもらう努力をしないといけないんです。
関連
・2018年のブロックチェーンビジネスを振り返る~概念実証から実用フェーズへ
HashHubではブロックチェーンエンジニア集中講座を実施しています。2週間集中して最速でブロックチェーンエンジニアになるプログラムを開講しています。お問い合わせはHashHubへ。