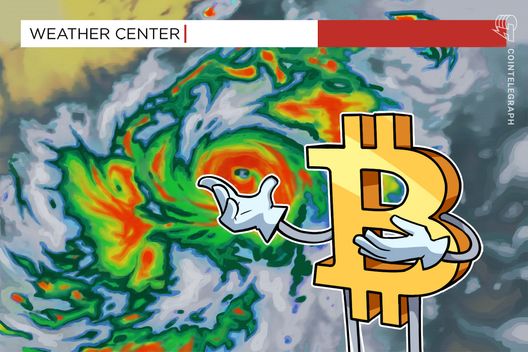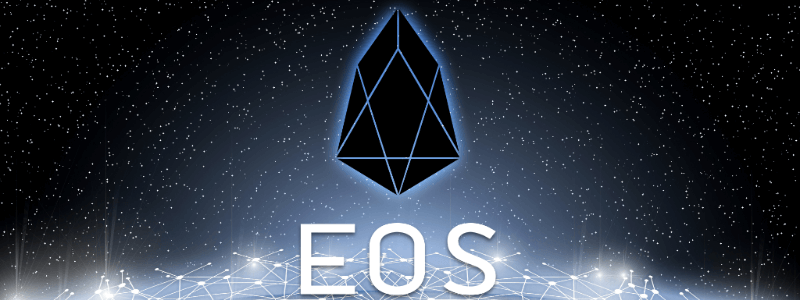

EOS(イオス)が、イーサリアム(Ethereum)に追随するスマートコントラクトプラットフォームとして頭角を現しつつあります。
EOSの基本設計は、BGFT形式のPoSにより21のバリデータノードがブロック生成をします。これにより、イーサリアムよりはるかに多くのトランザクションを処理することができますが、21のノードがブロック生成をすることについて、一般的にはEOSは分散化をある面で捨てていると評価されることが多いです。そして、これはEOSに対する批判的な意見の対象でもあります。
しかし、このことがEOSは分散化していないと評価するのは短絡的であると筆者は考えています。
分散性を獲得していくEOS(イオス)
コーネル大学のコンピューターサイエンティストのエミン・ギュン・サイレール氏(Emin Gün Sirer)の発表を紹介します。
サイレール氏によると、ビットコインでは90%のハッシュレートを、16のマイニングプールが保持していて、イーサリアムでは90%のハッシュレートを11のマイニングプールが保持している。さらに、ビットコインでは51%のハッシュレートを、4のマイニングプールが保持。イーサリアムでは51%のハッシュレートを3のマイニングプールが保持していると報告しています。
これに対して、EOSは約100の候補ノードから上位21のノードを常に選出しています。
サイレール氏は、このようなBFT形式のDPOSの方が、実は分散化しているのでは?という問題提起を投げかけています。これは重要な指摘です。
以前、ビットコインを支持する人は、ビットコインよりイーサリアムのほうが集権的であると考えていました。しかし、いつのまにかにイーサリアムではヴィタリック・ブテリン(Vitalik Buterin)の影響力が少しずつ小さくなりつつあり、クライアントについてはビットコインよりイーサリアムのほうが多様性が生まれつつあるという事実もあり、徐々に分散性を獲得していった事例はあります。
EOSに関しても、相互投票やEOSコア仲裁フォーラム(ECAF)のガバナンスモデルなどはまだ未成熟であり、これから改善されるべき点は多くありますが、徐々に今以上に分散性を獲得していく可能性もあるでしょう。
EOS(イオス)の分散性については考え直す余地あり
サイレール氏の発表では、主要マイニングプールやバリデータの数を例にあげていますが、「分散性の評価」に関しては、非常に難しいです。クライアントの種類と分散性・トークンのディストリビューション方式・開発者グループの構成・コードのアップデート方法など、多くの観点で評価をする必要があります。
EOSの分散性・ガバナンスについては、上述したブロック生成者の分布だけではなく、より深い考察が必要と言えるでしょう。
なお、現在、EOS上のアプリケーションのトランザクション数では、イーサリアムと比較をして大幅に上回っています。下記は、DappRadarからのEOSとイーサリアムのゲーム系プロジェクトの利用者数の画像の引用です。(データは12月1日時点)


(出典:DappRadar)
最もこのトランザクション数も、そもそもEOSを使うのだからアプリ自体がトランザクションが生成されやすい設計になっていたりするので、単純比較はできないことは注意が必要と言えるでしょう。
しかし、そのトランザクション性能が分散性を犠牲にしているからこそ、発揮されているという点に関しては、ブロック生成者の分散性という観点でビットコインやイーサリアムと引比較してほとんど変わらず、考え直す余地は十分にあるということが本コラムの趣旨でした。
今後、EOS上にはアプリケーションが増えることが予想されますが、これは常に考える必要があるでしょう。
関連
・次に来るブロックチェーンと期待されるEOS(イオス)の概要【HashHubイベントレポート】
・イオス(EOS)
ブロックプロデューサーに聞く、EOS(イオス)事情【HashHubイベントQ&Aセッション】
参考
・Smartereum
HashHubでは、ブロックチェーン業界で働く人のためのコワーキングスペースも運営をしています。利用お問い合わせはHashHubへ。