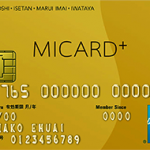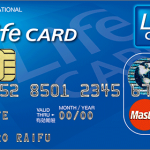近年、新しい資産運用サービスとして認知度を高めている「ロボアドバイザー」サービス。
気軽に資産運用が出来るメリットとは別に、頭を悩ませるのは税金周りの問題。
特にサラリーマンとして働いている人で確定申告を必要としない方、知っておきたい部分と言えるでしょう。
今回は、ロボアドバイザーにおける確定申告にフォーカスを当てて、税金に関して必要な知識や対応について説明します。
ロボアドバイザーの利益は申告分離課税

まず前提としてロボアドバイザーで発生した利益は申告分離課税に分類されます。
申告分離課税とは、株式等の譲渡により所得が生じた場合のように、他の所得とは分離して税額を計算、確定申告によって納税する課税方式を指します。
会社からの給料や収入は総合課税に分類され、最高税率55%が掛かる反面、ロボアドバイザーをはじめとした株式投資などは申告分離課税となり、税率は一律20.315%で抑えることが出来るのです。
特定口座(源泉徴収あり)を選べば確定申告は不要
今回は楽天証券が運営するロボアドバイザー「楽ラップ」を例に解説します。
楽ラップを使う場合は、事前に楽天証券の口座開設が必要。
この口座開設時に3つの口座タイプから選択が可能となります。
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 一般口座
「特定口座(源泉徴収あり)」を選択することで確定申告を行わずに済むのです。
確定申告を行う手間を省きたい方は、口座開設時に「特定口座(源泉徴収あり)」を選択しましょう。
口座の種類によって対応するべきことが異なる
実際に作成できる3つの口座タイプによって確定申告に対する対応は異なります。
一般口座
一般口座を選択すると、基本的には確定申告は必須となります。
作業としては、実際に出した運用益に対する税金の計算・確定申告・納税まですべて自分自身で行わなければならないために、投資初心者にはおすすめません。
3つの口座タイプの中で、最も手間は掛かると言えます。
特定口座(源泉徴収なし)
この口座を利用する場合は、証券会社から付与される年間取引報告書を使って内容を記入。
自分自身で確定申告を行う必要があります。
しかし、年間取引報告書を基に確定申告を行う為に、確定申告手続き自体は簡単になります。
確定申告に慣れておきたい方のステップとして、おすすめです。
特定口座(源泉徴収あり)
この口座を利用している場合は、確定申告などの手続きは必要ありません。
煩わしい手続きが嫌いな方にはおすすめです。
アドバイザー型のロボアドバイザーはNISA口座で非課税にすることも可能

ロボアドバイザーは主に「アドバイス型」と「投資一任型」に分かれます。
アドバイス型は、利用者の状況に応じて適切なポートフォリオを提案してくれるシステム。
ロボアドバイザーのアドバイスを取り入れながら、自分で運用を行う自由度の高い方法と言えるでしょう。
投資一任型は、ロボットが自動で資産運用を行うシステム。
投資における実際の発注や運用、また、運用途中における資産配分の変更など、実際の運用まで行う機能を担います。
ロボアドバイザーはNISA口座を使って非課税にすることは可能ですが、アドバイス型のロボアドバイザーのみにしか対応していません。
NISAの利用によって非課税になるメリットはありますが、アドバイス型は自分自身で運用をすべて行わなければならず、ある程度の時間と手間を要するデメリットが存在します。
「初めて投資を行う」という投資初心者の方は、すべての運用周りを自動で行なってくれる投資一任型を選択するのがおすすめです。
おすすめのロボアドバイザー3選
確定申告を不要にできないロボアドバイザーもある

楽ラップを使えば、楽天証券の口座開設時に「特定口座(源泉徴収あり)」を選択することで、確定申告を不要にすることが可能です。
しかし、他のロボアドバイザーでは、特定口座に対応していないサービスもあります。
大手ロボアドバイザーであるTHEO(テオ)やWealthNavi(ウェルスナビ)は対応していますが、必ず事前に特定口座を選べるかの確認は行いましょう。
確定申告が不要でも申告して得するケースも

ここまでロボアドバイザーの確定申告について説明しました。
「特定口座(源泉徴収あり)」を選択することで、確定申告が不要となり、投資初心者にもおすすめ。
しかし、特定口座を利用していて、本来は確定申告をする必要がない場合でも、確定申告をすることで税金が取り戻せるケースがあります。
この項目では、確定申告が不要でも申告することで得するケースを解説します。
他の株式などの取引で損失がある
他の株式などの取引で損失がある場合は、確定申告をすることで得するケースがあります。
このケースは「損益計算」と呼ばれており、「1月〜12月までに行われた売買を計算し、その利益と損失を合計して、最終的に利益が出たか損失になったかを算出すること」と定められています。
説明しても分からない点も多いはずなので、例を変えて説明します。
例えば1年間の運用実績が、下記の場合で考えてみましょう。
- THEOで3万円の利益
- WealthNaviで2万円の損失
損益通算を行わなければ、THEOの3万円から税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が徴収されます。
この計算によって、納める税額は約6,094円です。
一方、損益計算を行なった場合はTHEOの利益からWealthNaviの損失分をマイナスすることが出来ます。
その為、利益分の1万円に対してのみ税率20.315%が掛かるのです。
納める金額は約2,032円。
6,094円 – 2,032円 = 4,062円も節約できるのです。
今回は小さな金額で説明しましたが、運用している金額が大きくなれば、より損益通算の価値を実感できるでしょう。
昨年までの株式などの損失で繰越控除を受ける
もし昨年までの株式損失などがある場合は、「譲渡損失の繰越控除」という方法が使えます。これは「その年のマイナス分を向こう3年の利益と相殺できる」制度を指します。
年間ベースでマイナスが確定した場合、翌年の3月15日までに税務署に確定申告する必要があります。
これを事前に行っておくことで、そのあと3年は、利益が発生した場合でも損失の範囲内であれば税金を取られることはありません。
口座の種類とロボアドバイザーのタイプは事前に確認を

今回はロボアドバイザーサービスを利用した際の確定申告に焦点を当てて、説明を行いました。
確定申告については口座の種類とロボアドバイザーのタイプによって大きく分かれます。
講座の種類については、一般口座・特定口座(源泉徴収なし)・特定口座(源泉徴収あり)によって確定申告の有無も変わります。
また、NISAを利用出来るのは「アドバイス型」と呼ばれるサービスのみで利用可能であることも本文中でお話しました。
一括りでロボアドバイザーの税金と言っても、選択する口座やサービスによって大きく対応は変わります。
記事内でお話ししたポイントを踏まえて、是非、確定申告を上手に乗り切りましょう。
この記事が、ロボアドバイザー利用における確定申告に悩む方の参考になれば幸いです。