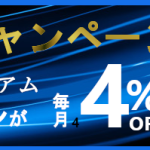iDeCoの節税効果に興味があるという方や、iDeCoを利用した資産運用を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、iDeCoで節税できる金額には上限があり、会社員、公務員、自営業者でそれぞれ上限金額が異なるため、注意が必要です。
そこで今回は、iDeCoで定められた掛金の上限をはじめ、iDeCoで資産運用を始めるときのポイントについて紹介します。
iDeCo(イデコ)で節税できる金額には上限がある

iDeCoの掛金は所得控除の対象となります。しかし、所得控除できる金額には上限が決まっており、公務員、会社員、自営業者でそれぞれ上限となる金額が異なるのです。それぞれの上限額は次の通りです。
| 年金の加入状況 | 内容 | 拠出できる掛金の上限 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者など | 月額6万8,000円まで (年額81万6,000円まで) |
| 第2号被保険者 | 企業型確定拠出年金に加入していない会社員 | 月額2万3,000円まで (年額27万6,000円まで) |
| 企業型確定拠出年金に加入している会社員 | 月額2万円まで (年額24万円まで) |
|
| 確定給付企業年金の加入者・公務員 | 月額1万2,000円まで (年額14万4,000円まで) |
|
| 第3号被保険者 | 専業主婦など | 月額2万3,000円まで (年額27万6,000円まで) |
自営業者の場合、月額6万8,000円(年額81万6,000円)までの掛金が認められているのに対して、確定給付金型年金の加入者や公務員の場合、月額1万2,000円(年額14万4,000円)までの掛金しか認められていません。なぜなら、企業年金などに加入している方は、将来年金を受け取る際に公的年金に上乗せして年金を受給することができるからです。
また、自営業者の場合は国民年金のみですが、会社員の場合は厚生年金に加入しているため、基礎年金(国民年金)と厚生年金を受け取ることができるため、iDeCoの掛金の上限が自営業者よりも低くなっています。
iDeCo(イデコ)で受けられる節税に関するメリットは?

iDeCoに加入することで受けられる節税メリットは3つあります。
それぞれの内容について、もう少し詳しく説明します。
掛金全額を所得控除することで所得税と住民税が節税できる
所得税と住民税を計算するもとになる課税所得額は、すべての収入額から経費と各種所得控除額を差し引いた後の金額のことをいいます。所得税と住民税の税率は、課税所得額に応じて決められています。
つまり、課税所得の金額を少なくするこができれば、その分節税できることになります。
iDeCoは、掛金全額を所得控除として差し引くことができるため、所得税と住民税の両方の節税につながります。
運用益が非課税
通常、投資信託などの運用益には約20%の税金がかかります。
例えば、資産運用によって10万円の利益が出た場合、そこから2万円強の税金を支払う必要があるため、手元に残る金額は8万円弱となるのです。
しかし、iDeCoを利用して運用した場合の運用益は非課税なので、10万円の利益が出た場合、手元に残る金額は10万円のまま、約2万円分の税金を節税することができます。
iDeCo(イデコ)で運用した資金の受け取り時にも控除が受けられる
iDeCoで運用した資金は、60歳以降になれば一時金または年金として受け取ることができます。
一時金として受け取った場合は、「退職所得控除」を利用することができ、年金として受け取った場合は「公的年金等控除」を利用することができます。
こちらも所得税や住民税のときと同様に、受け取った金額から退職金控除または公的年金等控除を利用することができるため、その分節税することが可能です。
iDeCoを始めるならSBI証券がおすすめ!
iDeCo(イデコ)で資産運用を始めるときのポイントや注意点

iDeCoは節税しながら老後資金の形成ができるというお得な資産運用の方法ですが、もちろん注意しなければいけないこともあります。
iDeCoで資産運用を始める際、忘れてはならないのが、iDeCoは貯蓄ではなく、あくまでも投資だということです。
銀行に預金しておくのであれば元本割れをすることはありませんが、iDeCoは掛金を運用する商品ですので、元本割れのリスクがあります。
また、他にも注意しなければいけないポイントがいくつかあります。
原則60歳まで引き出すことができない
iDeCoは、原則として60歳まで引き出すことができません。
例えば、子どもの教育資金や住宅資金など、60歳前にまとまった資金が必要になる予定があるという方は、iDeCo以外の方法を検討するようにしましょう。
原則中途解約することができない
iDeCoは原則として中途解約ができません。
まったくできないということではありませんが、解約には要件があり、要件が満たされていないと解約することができません。そのため、解約することは非常に困難です。
掛金の支払いが停止できたという場合も、手数料は支払い続けなければならないので、注意してください。
手数料がかかる
iDeCoの口座開設時や運用時には各種手数料が必要になります。
しかし、iDeCoを利用することで掛金分の控除を受けることができるため、口座維持の手数料を差し引いたとしても節税できる金額があるので、手数料の負担が大きいと感じることは少ないといえます。
ただし、利用する金融機関によって手数料が異なるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
加入資格がある
iDeCoには、加入資格があります。
20歳未満の方と60歳以上の方、海外に居住している方は加入することができません。
掛金の変更は年に1回のみ
iDeCoの掛金は、公務員、会社員、自営業者で上限が決められていますが、その範囲内であれば掛金を変更することができます。
ただし、掛金の変更ができるのは年に1回のみなので、掛金の変更を希望する場合は十分に検討してから行うようにしましょう。
iDeCoを始めるならSBI証券がおすすめ!
iDeCo(イデコ)で老後の資金を準備しておくことは重要!

自営業者の場合の国民年金の受給額は、満額で約6万5,000円、平均受給額は5万5,000円です。
国民年金部分を含む厚生年金の受給額の平均は約14万5,000円といわれているので、自営業者の方は国民年金以外で老後の資金を準備しておくことが非常に重要です。
自営業者が拠出できるiDeCoの掛金の上限は、月額6万8,000円まで、年額では81万6,000円までとなっています。iDeCoで老後資金の準備を行う場合、国民年金にプラスして老後の資金を確保できるだけではなく、節税対策にもつながります。
自営業者はiDeCo(イデコ)と一緒に国民年金基金の加入がおすすめ
自営業者の方の老後の資金の準備としては、iDeCo以外にも、「国民年金基金」に加入するという方法があります。
国民年金基金は、自営業者の方も会社員と同様に、誰もが受給できる国民年金に、国民年金基金の積み立て分を上乗せすることができる制度です。
iDeCo(イデコ)と国民年金基金の違い
iDeCoと国民年金基金の大きな違いは、国民年金基金は掛けた分のお金が減ることはないという点です。iDeCoはあくまでも投資なので、上手く運用できれば資金を増やすことができますが、元本割れのリスクもあります。そのため、できるだけリスクは避け、確実に資金を増やしたい場合は国民年金基金の加入がおすすめです。
国民年金基金は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者および60歳以上65歳未満の方、海外に居住していて国民年金に任意で加入している方だけが加入できる制度です。
自営業者の方の場合は、iDeCoだけではなく国民年金基金の加入も検討してみることをおすすめします。
iDeCo(イデコ)で節税できる上限金額を確認して資産運用をしよう!

iDeCoには、公務員、会社員、自営業者によって掛金の上限が決められています。同じ会社員でも会社の企業年金などに加入している場合は、上限の金額が変わるので注意しましょう。
iDeCoは、老後の資産形成ができるだけではなく、節税効果も期待できる優れた制度です。
ただし、iDeCoの加入には注意点もあるので、今回紹介した内容を参考に、注意点も理解した上で加入するようにしましょう。
iDeCoを始めるならSBI証券がおすすめ!