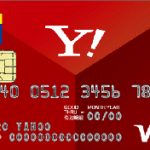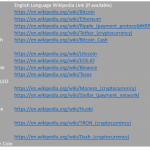みなさんは少額投資非課税制度(NISA)をご存知でしょうか。最近テレビCMなどで目にすることも多いため、名前は聞いたことがあるという方も多いかもしれません。少額投資非課税制度(NISA)は、国が用意した、少額で長期に資産運用をするためのお得な制度です。
少額といっても人それぞれ感覚が違うと思いますが、少額投資非課税制度(NISA)の場合は、月々10万円、年間120万円が制度の対象となる上限金額です。もちろん10万円/月以下であれば対象になりますので、コツコツ毎月1万円を資産運用に、という方でも利用できます。
また、少額投資非課税制度(NISA)には、利用方法や対象の年齢によって、3種類のNISAがあります。今回は、3種類それぞれ紹介しながら、少額投資非課税制度(NISA)について詳しく解説します。
NISAの種類は?
少額投資非課税制度(NISA)には、NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの3種類の制度があります。それぞれ後ほど詳しく解説しますので、ここでは簡単に概要を紹介します。
まず、それぞれのNISAで、対象年齢が異なります。成人以上の方は、一般NISAかつみたてNISAから選択します。
ジュニアNISAは、成人未満の方を対象にした制度なので、本人が始めるか、もしくは、将来の資産運用のために親が子どもの口座を作っておくということもできます。
その他、大きく違うのは、年間の投資上限金額と購入した後非課税になる期間です。さきほど紹介したとおり、ジュニアNISAはそもそも年齢で利用できるか否かが決まるため、一般NISAとつみたてNISAで比較すると、一般NISAは年間投資上限金額が120万円で、非課税期間が5年、つみたてNISAは年間投資上限金額が40万円で非課税期間が20年です。
資産運用する金額を大きくして、期間を短くするか、少額にして期間を長くするか、資産運用のスタイルによって選択しましょう。
| 種類 | 一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20歳未満 |
| 運用方法 | 通常買付・積立 | 積立 | 通常買付・積立 |
| 年間投資上限金額 | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
| 非課税になる期間 | 5年 | 20年 | 5年 |
※今後、成人年齢が引き下げられた場合は変更になります。
NISAとは?
NISA(一般NISA)は、2014年に開始された非課税制度で、以下の特徴があります。
- 日本に住む20歳以上の方が使える制度
- 株式や投資信託などの利益に対する税金が非課税に
- 年間120万円までの投資に対して非課税に
- 口座開設できる期間は、2014年から2023年まで
- NISA口座の非課税期間は、投資した年から最長5年間
まとめると、年間120万円まで投資できる枠があり、その投資に対しての利益は最長5年間は非課税になるという制度です。ひとりひとり年間120万円という上限が決められていて、かつ、口座開設の期間も2023年までと決められているので、早い段階で利用しておかないと損です。
また、NISA口座は、ひとり1口座と決められています。さまざまな証券会社でお得なプログラムと共に提供されているため、自分にあった条件のNISA口座を見つけて、申込みをしましょう。
NISAの注意点は?
お得な制度であるNISAですが、いくつか注意点があります。
まず、証券口座とは別にNISA口座を申し込む必要があることです。
1年毎に投資枠が定められているため、証券会社によっては、年末の一定期間は口座開設を受け付けていないこともあるようです。NISA口座を開設したい証券会社が決まったら、早めに口座開設手続きを始めるのが良いです。
口座開設手続きを早めに行っておく方が良い理由がもう一つあります。それは、各年毎に決められた120万円の投資枠は権利を翌年に繰り越せないということです。口座開設が2023年までと定められている以上、2019年には口座開設をしないと、最大5年と定められている枠がフルに使えなくなってしまいます。
同じ年に別の証券会社のNISA口座に移管することはできませんが、1年毎の単位(12月までの一単位が終了したタイミング)では、証券会社を変えることもできるため、2019年にいずれかの証券会社でNISA口座を開いておくことをおすすめします。
NISA口座ならではの注意点もあります。NISA口座は、投資に対する利益が非課税になることがメリットですが、通常の証券口座ではできる、他の証券口座で発生した利益や損益とは、損益通算ができません。また、通常の証券口座であれば、損失が出た場合も翌年以降3年間は損失を繰り越して、他の年で利益が出た場合に相殺できますが、NISA口座の場合はこの繰越もできません。
最後に、NISA口座のもう一つのメリットとして、投資した株式等から出た配当金に対する税金も非課税になるのですが、非課税の対象となるのは、配当金受取方法で「株式数比例配分方式(証券口座の入金される方式)」を選択する必要があります。通常の受け取り方法では非課税とならないため、受け取り方法をチェックしておきましょう。
つみたてNISAとは?
次に、つみたてNISAについて解説します。
つみたてNISAは、一言で表現すると、NISA口座を積立投資に特化させたNISAで、NISA口座と比較すると、年間の投資枠が120万円から40万円に減る代わりに、非課税となる期間が5年から20年間に大幅に長くなります。
つみたてNISAの注意点は?
つみたてNISAの注意点は、さきほどのNISA口座の注意点と同様の部分に加えて、以下の点が挙げられます。
まず、NISA口座とつみたてNISA口座は、いずれか1口座の選択性になっています。証券口座の移動と同様に1年毎に切り替えることはできますが、両方を同時に使うことはできないため、開設前によく検討するようにしましょう。
また、つみたてNISAで投資できる商品はNISA口座に比べるとかなり少なくなります。国が定めた厳しい条件をクリアしている商品だけが対象商品になっているためなので、厳選された商品ではありますが、投資したい商品が揃っているか、こちらも先に確認してくと良いです。
ジュニアNISAとは?
最後にジュニアNISAについて解説します。
ジュニアNISAはその名の通り、ジュニア用のNISAで、20歳未満の方を対象にしたNISA口座です。
もちろん、多くの場合は20歳未満の本人が資産運用を始めたいということではなく、親が子ども将来のために投資をするケースの方が多いでしょう。多くの証券会社では親の口座があれば、子どもの口座も申し込むことができますので、利用する場合は併せて申し込みましょう。
ジュニアNISAもルールはほとんどNISA口座と同様ですが、年間の投資枠は120万円ではなく、80万円になります。
ジュニアNISAの注意点は?
ジュニアNISAの注意点も、NISA口座の注意点と同様の部分に加えて、非常に重要な点が、ジュニアNISAに入金した資金は、18歳までは払出しができないことです。
ジュニアNISAは、もともと子どもの進学等の「将来必要な資金を準備するための長期投資」を目的に作られた制度という側面が大きいため、たとえ全く金融商品を購入していないという場合でも、引き出しができません。
少額投資非課税制度(NISA)の口座を開設できる証券会社は?

NISAとつみたてNISAの口座はいずれか1つしか作成できないため、口座開設は慎重に行いたいものです。
2019年、NISAの口座を受け付けている人気の証券会社を一部ご紹介します。
楽天証券のつみたてNISA
ショッピングから旅行、スマホまで幅広くサービスを展開している楽天グループの一つ、楽天証券。
金融庁が定めるつみたてNISAの対象商品が162本あるうち、楽天証券はそのうちの150本もの投資信託を取り扱っています。
毎月積立に加え「毎日積立」もできるため、より細かな分散投資も可能となります。
一番の魅力は楽天スーパーポイント
生活に根ざしたサービスを多数展開している楽天であるため、積立代金の引き落としは楽天銀行や楽天カードなども選択可能です。
楽天カードで引き落とせば楽天スーパーポイントも還元されるためお得に。
そして、積立代金を楽天スーパーポイントで支払うこともできるのが最大の強み。
投資信託の残高や毎月の積立額に応じてポイントの付与もされるため、一つでも楽天のサービスを利用している人にはメリットの多い口座になるでしょう。
マネックス証券の一般NISA
売買手数料や買付け手数料など、何かと必要になる運用コストを抑えたいならマネックス証券がおすすめです。
米国株・中国株など外国株の取扱銘柄の豊富さで人気なことに加え、NISA口座で海外ETFを含む外国株の買い付け手数料が無料なのはマネックスだけ。
国内株の売買手数料も無料なため、NISAで国内株、外国株への投資に興味がある人にぴったりです。
そのほかセゾン投信やDMM.com証券なども勢いのある証券会社として注目を集めています。
初心者には少額投資非課税制度(NISA)がおすすめ!

今回は、3つのNISA制度をご紹介しました。NISA口座、つみたてNISA口座それぞれにメリットはありますが、つみたてNISA口座は投資できる対象商品が絞られていることもありますし、まずは自分にあったNISA口座を見つけ、申し込んでみるところから始めるのがおすすめです。
5年間という投資枠が決まっているため、2023年以降制度が延長される可能性もありますが、2019年中に申し込み、制度のメリットを最大限活かすのが良いと思います。